AI検索「無断使用訴訟」で既存メディアは勝てるのか?

止まらないAIの進化と侵食。日本でも大手新聞3社が共闘を始めたが......
読売、朝日、日経の大手新聞3社が、記事を無断使用しているとして米国のAI検索企業「パープレキシティ」を訴えた。AI検索企業vs大手メディアの闘いはどうなるのかを予測する!
* * *
■著作権問題というよりビジネスの問題!?AIの進化が止まらない。
最近はパソコンでもスマホでも、検索をするとAIが情報を集めて答えてくれることが多くなった。とても便利だ。
しかし、その一方で情報を収集される側の大手メディア3社(読売新聞社、朝日新聞社、日本経済新聞社)が、8月に米AI検索サービス大手「パープレキシティ」を著作権侵害などで訴えている。
いったい、何が問題になっているのか。ITジャーナリストの三上 洋氏に聞いた。
「パープレキシティは、特に検索に力を入れているサービスです。例えば『最近の著作権侵害について教えて』と入力すると、AIがまとめた文章のほかに『読売新聞』『朝日新聞』『日経新聞』『ロイター』など、どの記事を参考にしたのかがわかるようになっています。
そして、そのロイターのアイコンをクリックすると参考にしたロイターの記事に飛んでいくので、詳しく知りたければクリックすればいい。また、ニュースソースが明記されているので、まとめた回答も信頼性が高いと感じる。ユーザーにとっては、とてもありがたいサービスです。
ただ、問題なのは参考にした記事とものすごく似た回答が出てくること。メディア側からすれば『うちの記事を勝手に使ってるよ』ということになります。また、場合によっては回答の内容が間違っていたりすることもあります。すると『うちの記事がソースだって言ってるのに間違った情報が載ってて、うちの信用が落ちるよ』となる。
さらに一番重要なのは、ユーザーがパープレキシティのまとめた回答を見て満足してしまって、ソースとなったメディアの記事を見に行かなくなること(ゼロクリックサーチ)です。
ほかの検索エンジンなどの場合は、見出しなどから元の記事に飛んで、ページビューが増える場合がありますが、パープレキシティの場合は、参考にしたメディアのページビューが落ちるでしょう。
それで大手メディアは『勝手に記事を参考にしてまとめを作り、ページビューも増えないのは許せない』と怒って、訴えたのだと思います。ですから、著作権の問題よりもビジネスの問題のほうが大きいのではないでしょうか」
読売新聞は約21億6800万円を、朝日新聞と日経新聞(共同提訴)はそれぞれ22億円の損害賠償をパープレキシティに請求をしている。
では、この裁判の結果はどうなるのか?
「パープレキシティは、この秋から報道機関や出版社に対して、収益の一部を分配する仕組みを作ると表明しています。また、このサービスに参加するメディアに分配金として63億円を用意しているとも言っています。
もし、これを本当にやって、今回訴えている新聞社側に収益が入るのならば、手打ちになる可能性はあります。
ちなみに生成AIの『チャットGPT』を提供している米『オープンAI』社は、米『ワシントン・ポスト』や『AP通信』、英『ファイナンシャル・タイムズ』などと提携しています。今後は日本もそうした流れになっていくのではないでしょうか」
■メディアは収入源をどんどん破壊される!もうひとつの未来があるかもしれないというのは、知的財産法を専門とする東京大学先端科学技術センターの玉井克哉特任教授だ。
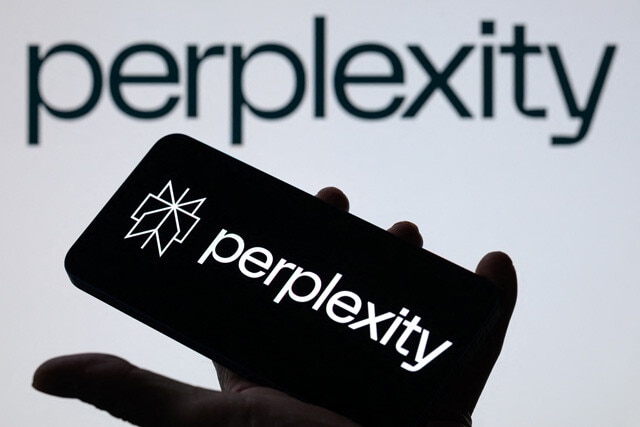
「パープレキシティ(Perplexity)」は、元グーグル、元オープンAI、元メタなどのAI研究者によって2022年に公開されたAI検索エンジン。CEOはアラビンド・スリニバス氏
「パープレキシティは、時価総額が180億ドル(約2兆6700億円)の巨大企業です。
読売新聞や朝日新聞、日経新聞から、それぞれ22億円ほどの損害賠償を請求されても、大きな痛手にはなりません。裁判に負けて総額66億円を支払おうとも、パープレキシティは今の商売のやり方を変えないでしょう。
それよりも問題なのは、IT系の企業が既存のメディアの収益源をどんどん破壊しているということです。そして、メディアが収入源を破壊されることに文句をつけようとすると著作権侵害くらいしかない。
例えば、今回でいうとパープレキシティのまとめた回答が、自分たちの記事にそっくりだと新聞社が訴えている。しかし、著作権法は人間の創作物が似ているか似ていないかを争うもので、具体的に表現が似ていなければ、著作権侵害にならないんです。機械が情報をまとめて意味の通る文章を出力することまでは考えていません。
それに、AIに『著作権侵害にならないように表現を少し変えて』と入力すれば、対応してくれるはずです。オリジナルの文章がすぐ作れます。すると、これまでは『AIが自分たちの記事をパクった』と訴えられたけれど、それもできなくなる。
さらに、今後はAIが自分でニュースを取りに行くこともできるようになるという人もいます。でも、そのニュースは誰が生み出すのか。人間にとって重要な1次情報は、人間が取材して取るほかありません。AIが価値を創造することはない。
例えば『ゼレンスキー大統領について教えて』というと『元コメディアンで......』とみんな同じような内容になってしまう。そういう没個性的な文章や画像、音楽に慣れた社会になってしまう。AIが作った文章や画像、音楽以外は知らない人が増えてしまう。未来がそれでいいのかということなんです。
だからこそ、この過渡期に著作権法以外に新しい法律などを作って、1次情報を提供する会社や人の権利を守らなければいけないし、価値を創る人にお金が入るようにしなければいけないんです」
AIの進化でわれわれの生活はとても便利になっている。しかし、その一方で失うものも増えている。何を残して何を捨てるのか。今、その選択が迫られているのかもしれない。
取材・文/村上隆保 写真/時事通信社
記事提供元:週プレNEWS
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
