「最期の瞬間を看取れなくてもいい」3000人のお看取りをしてきた在宅医療のスペシャリストに聞く「後悔のない人生の送り方」
更新日:
イチオシスト:イチオシ編集部 旬ニュース担当
注目の旬ニュースを編集部員が発信!「イチオシ」は株式会社オールアバウトが株式会社NTTドコモと共同で開設したレコメンドサイト。毎日トレンド情報をお届けしています。
クリニックを立ち上げて25年、3000人のお看取りをしてきた在宅医・永井康徳氏が『後悔しないお別れのために33の大切なこと』(主婦の友社)を出版。
【動画】人生、最期まで“我が家”で…〜家族で向き合う「在宅医療」〜
「たんぽぽクリニック」(愛媛・松山市)で在宅医療に取り組む永井先生が、命についてやさしくていねいに書いた一冊。“悔いが残らない最期”を迎えるためにはどうすればいいのか…多くの患者の最期に寄り添ってきた永井医師が説く、後悔のない人生の送り方とは。
 ▲医療法人ゆうの森「たんぽぽクリニック」永井康徳氏
▲医療法人ゆうの森「たんぽぽクリニック」永井康徳氏
――永井先生が“在宅医療に専念しよう”と決意したきっかけを教えてください。
「医学部1回生の時、へき地医療のフィールドワークを体験しました。その時に改めて“こういう場所では医療を必要としている人が多いんだな”ということを感じましたし、他の医者がやらないことをやれば、自分の能力を生かして社会や地域に貢献できるのではないかと考えました。
その志が一層強くなったのは、へき地の診療所の所長として勤め始めた頃のこと。高齢の患者さんが多く、診療所に通えない人がいたら、自然と在宅医療を始めるようになり、気がついたら、4、5年で地域の3分の1ぐらいの患者さんを看取る状況になっていました。
2000年頃から高齢者が増え始め、在宅医療の重要性が増しているのを肌で感じていましたし、さまざまな経験を通して、もっと在宅医療を突き詰めてみたいと考えるようになったのです。
しかし、しっかりとした在宅医療を行うには、外来診療や病棟診療をしながらでは限界がある。そこで、在宅医療に24時間対応できる専門クリニックを開業しようと決意しました」
――クリニックを立ち上げて25年、特に大変だったことはありますか。
「一番大変だったのは、24時間体制を維持することでした。最初は一人で始めたので、当然対応するのが難しい。看護師さんの力を借りながら頑張っていましたが、このまま10年、20年と続けていけば自分が疲弊してしまう。そこで、疲弊しないシステムを構築し、複数の医師で体制を整えることを決めました。
しかし、これもまた簡単ではありませんでした。何人もの医師や職員が、それぞれの意見や方針を統一し、情報を共有するシステムをしっかり構築していく必要があったからです。
また、当時の松山は今以上に保守的で、在宅医療を専門に行う医者は珍しく、出る杭は打たれる。『全時間帯1人でやるなんて、永井先生は嘘ばかりついている』と言われたことも。地域で新しい取り組みを始めるには、さまざまな苦労がありました」
――そんな努力の甲斐もあり、先生の信念に賛同したチームが結成。「たんぽぽクリニック」では、「望みかなえ隊」が、患者さんのさまざまな夢や希望をかなえるべく奮闘していますが、皆さんの中で共有している思いはどのようなものなのでしょう。
※「望みかなえ隊」とは…医師や看護師、ソーシャルワーカー、ケアマネージャー、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、調理師、鍼灸マッサージ師など、さまざまな専 門スタッフが参加するチームの名称。
「私たちの最終的なゴールは、患者さんの看取りです。治療だけをするのではなく、人や家族、生活や地域を見て、その患者さんがどうすれば納得できるのか、そして最終的に亡くなる時も“これで良かった”と思えるかという点を重視しています。
意思決定、つまりは“どういう選択肢があってどういう選択をするのか。どのように生き、何を大切に思って、最期をどのように迎えたいのか”、そのプロセスを患者さんと一緒に悩みながら考えていくことが大切。私は、そうした関わりを続けていく中で、患者さん一人一人の人生はドラマだと感じるようになりました。
医者や看護師といった専門職がそれぞれの役割を超えて、患者さんの人生の最期に関わることを切ないことと捉えず、尊いことだと感じる。
例えば、お母さんが亡くなる前、お子様が成人を迎える時に開けられるようなタイムカプセルを作るなど、残された日々を患者さんが思い切り自分らしく生きられるよう、組織全体でサポートする。私たちは、患者さんのそういう想いを支援したいのです。
苦痛を和らげ、限られた命とどう向き合うかということに、みんなで寄り添っていきたいと思っています」
――在宅医療で奮闘する中、先生ご自身も進行がんを患われたそうですが、つらい経験を経て、何か変化はありましたか。
「医師というのは、“こんな検査や治療ができるようになった”と、どうしても技術ばかりに目がいって、ちょっと上から目線で当事者の気持ちを忘れがちになってしまうと思うんですよね。
自分の身に降りかからないとそういう気持ちになれないのかといったらそうではないのですが、実際に父を亡くし、47歳の時に自分自身が病気になったことで、患者さんの気持ちがより深く分かるようになったと思います。
私ががんになった時、子どもはまだ高校生でした。“クリニックをどうしよう。なぜこんな若くしてがんになるんだろう”と、本当の意味で患者さんやご家族の気持ちがより理解できるようになりました」

――本人が在宅医療を希望しても、家族が受け入れに難色を示すケースもあると思います。家族側の心得について、何かいいアドバイスはありますか。
「一番大切なのは、“本人の意思を尊重すること”です。もちろんできないこともあるかもしれませんが、本人にとっての最善は何か、そこに想いを馳せて考えることが大切です。
老老介護や独居でも、私たちで看取ることは可能です。そして患者さんやご家族の皆様に、いつも伝えているのは以下の3つです。
1.本人や家族が自宅で最期を迎えたいと望んでいるかどうか
2.医療は最小限でいいかどうか
3.最期の瞬間を必ずしも看取らなくてもいい
これらをしっかりと理解していれば、我々のサービスが入っていけます。“親の最期の瞬間を看取ることができなかった…”と後悔し、ずっと引きずってしまう方もいると思いますが、過去は変えられないとしても、その後悔や経験を、今後の自分の生き方や家族の看取りに生かすことはできますよね。そう考えると、ちょっとは気持ちが楽になるのかなと。
そして看取れなかったという事実よりも、“それまで自分がどう関わったのか”“本人が楽に生きられたのか”、これが一番大切だということを理解してほしい。
人は必ず死を迎えます。それを避けることはできません。死と向き合うか、向き合わないかでその人の選択肢や人生の終わり方が大きく変わってくると思います」
―― では逆に、患者さん側が家族に対して配慮することは?
「最終的には自分の身を託すことになるので、病気などの事実をありのまま家族に話しておくことでしょうか。また、遠慮をして自分の希望を伝えないままだと、家族は最善の選択ができなくなってしまいます。ご自身の意向をしっかりと伝えておくことが必要です。また、本人が強く望めば、最終的に独居でも看取ることはできるので、家族の負担を考えて在宅医療に切り替えられないなど、自分の希望を諦める必要はないと思います」
――先生が考える「幸せだった」と思える最期とは?
「幸せだと感じるかどうかは、個人によって違うと思います。ただ、死に向き合い、限られた命をどう生きるかを考え、自分らしく人生をやりきったと思えれば、“幸せなさよならだった”と言えるのではないでしょうか」
――本を読んで、エンディングノートを書いてみようと思いました。書くことに前向きではない人に、どのようにアドバイスしたらいいのでしょう。
「まず、エンディングノートをすべて埋める必要はありません。本の中で記した“もしもシート”のように、その日の気分で思いついたことを少しずつ書くだけでいいのです。医療に対する希望も、書いたことは後から気が変わっても全然いいんですよ。
もう一つ、本の中で“人生会議”という項目がありますが、延命治療するとかそういう難しいことではなく、“自分が何を大切に思って生きているのか、何が好きで何が嫌いなのか”を話すだけでもいいと思います。若くても、元気でも、死について話すことは大切で、目的は自分自身で考えることにある。
例えば、身近な人や著名人の死に直面した時、“自分はこうしたいけど、お父さんとお母さんはどう?”など、そういうことから少しずつ話していければいいのではないでしょうか」
――50歳を過ぎると、友人同士で死について話す機会も。しかしどうしても、暗い話になりがちです。もっと前向きに話すためのアドバイスはありますか。
「私の講演会でも、よく“ピンピンコロリで亡くなりたいか、介護を受けて亡くなりたいか”という話が出ます。やはり、ピンピンコロリで亡くなりたいという方が多く、大多数の方が手を挙げますが、さらに“明日亡くなってもいいと思えますか?”と聞くと、すーっと手が下がるんですよね。
そんな中、わずか数パーセント“ピンピンコロリであれば、明日亡くなってもいい”という方がいます。話を聞くと“私はやりたいことをやってきた。だから今日亡くなっても悔いはない”とおっしゃる。ただ長く生きるのではなく、“自分らしくいつ死んでもいい”と思える人たちがいる…これはすごいことだなと。
例えばですが、そこに向かって、自分らしくやりたいことをやりきる、死に向き合うという話は、非常に前向きですよね。
生き方の選択肢はたくさんあります。友人同士または家族間においても、“最期までこれが食べたい”“家族にこういうことを伝えたい”など、具体的な希望を話してみると、暗くなく前向きな話へと変わるのではないでしょうか。
明日心筋梗塞で亡くなるかもしれないし、事故で亡くなるかもしれない…それはみんな同じです。だからこそ、“あと何年自分に時間があるだろう”と、一度考えてほしい。
今はそういうアプリもありますし、人生の残り時間を意識してみると、意外と短いことに気づきます。その時間をどう使うか、どう社会に貢献するかを考えることが、前向きに死を捉えるきっかけになると思います。
人生会議を大切に…これからの自分や家族のために、一度人生の終わりを考えてみてはいかがでしょうか」
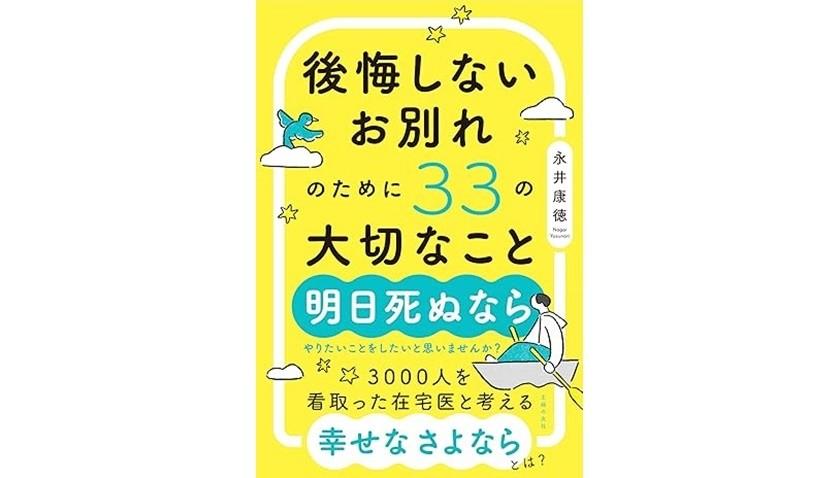 ▲『後悔しないお別れのために33の大切なこと』(主婦の友社)
▲『後悔しないお別れのために33の大切なこと』(主婦の友社)
【永井康徳 プロフィール】

医療法人ゆうの森 たんぽぽクリニック 医師
愛媛県のへき地診療所勤務の後、2000年に愛媛県松山市で、四国で初めての在宅医療専門のたんぽぽクリニックを開業。
「理念」と「システム」と「人材」のすべてを高いレベルで維持して在宅医療の質を高めることをめざし、現在は常勤医10人、職員100人の多職種チームで在宅医療を主体に、有床診療所、外来の運営も行っている。
平成22年には市町村合併の余波で廃止となった人口約1200人の町の国保へき地診療所を民営化し、開設4ヶ月で黒字化を達成。そのへき地医療への取り組みは平成28年に第1回日本サービス大賞地方創生大臣賞を受賞。全国各地での講演を行い、「全国在宅医療テスト」や「今すぐ役立つ在宅医療未来道場(通称いまみら)」「流石カフェ」など在宅医療の普及のための様々な取り組みを行っている。
コロナ禍で現地講演会が難しくなってからは、YouTubeで「たんぽぽ先生の在宅医療チャンネル」を開始している。
(取材・文/蓮池由美子)
【動画】人生、最期まで“我が家”で…〜家族で向き合う「在宅医療」〜
「たんぽぽクリニック」(愛媛・松山市)で在宅医療に取り組む永井先生が、命についてやさしくていねいに書いた一冊。“悔いが残らない最期”を迎えるためにはどうすればいいのか…多くの患者の最期に寄り添ってきた永井医師が説く、後悔のない人生の送り方とは。
 ▲医療法人ゆうの森「たんぽぽクリニック」永井康徳氏
▲医療法人ゆうの森「たんぽぽクリニック」永井康徳氏日々の活動と在宅医療への思い
――永井先生が“在宅医療に専念しよう”と決意したきっかけを教えてください。
「医学部1回生の時、へき地医療のフィールドワークを体験しました。その時に改めて“こういう場所では医療を必要としている人が多いんだな”ということを感じましたし、他の医者がやらないことをやれば、自分の能力を生かして社会や地域に貢献できるのではないかと考えました。
その志が一層強くなったのは、へき地の診療所の所長として勤め始めた頃のこと。高齢の患者さんが多く、診療所に通えない人がいたら、自然と在宅医療を始めるようになり、気がついたら、4、5年で地域の3分の1ぐらいの患者さんを看取る状況になっていました。
2000年頃から高齢者が増え始め、在宅医療の重要性が増しているのを肌で感じていましたし、さまざまな経験を通して、もっと在宅医療を突き詰めてみたいと考えるようになったのです。
しかし、しっかりとした在宅医療を行うには、外来診療や病棟診療をしながらでは限界がある。そこで、在宅医療に24時間対応できる専門クリニックを開業しようと決意しました」
――クリニックを立ち上げて25年、特に大変だったことはありますか。
「一番大変だったのは、24時間体制を維持することでした。最初は一人で始めたので、当然対応するのが難しい。看護師さんの力を借りながら頑張っていましたが、このまま10年、20年と続けていけば自分が疲弊してしまう。そこで、疲弊しないシステムを構築し、複数の医師で体制を整えることを決めました。
しかし、これもまた簡単ではありませんでした。何人もの医師や職員が、それぞれの意見や方針を統一し、情報を共有するシステムをしっかり構築していく必要があったからです。
また、当時の松山は今以上に保守的で、在宅医療を専門に行う医者は珍しく、出る杭は打たれる。『全時間帯1人でやるなんて、永井先生は嘘ばかりついている』と言われたことも。地域で新しい取り組みを始めるには、さまざまな苦労がありました」
――そんな努力の甲斐もあり、先生の信念に賛同したチームが結成。「たんぽぽクリニック」では、「望みかなえ隊」が、患者さんのさまざまな夢や希望をかなえるべく奮闘していますが、皆さんの中で共有している思いはどのようなものなのでしょう。
※「望みかなえ隊」とは…医師や看護師、ソーシャルワーカー、ケアマネージャー、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、調理師、鍼灸マッサージ師など、さまざまな専 門スタッフが参加するチームの名称。
「私たちの最終的なゴールは、患者さんの看取りです。治療だけをするのではなく、人や家族、生活や地域を見て、その患者さんがどうすれば納得できるのか、そして最終的に亡くなる時も“これで良かった”と思えるかという点を重視しています。
意思決定、つまりは“どういう選択肢があってどういう選択をするのか。どのように生き、何を大切に思って、最期をどのように迎えたいのか”、そのプロセスを患者さんと一緒に悩みながら考えていくことが大切。私は、そうした関わりを続けていく中で、患者さん一人一人の人生はドラマだと感じるようになりました。
医者や看護師といった専門職がそれぞれの役割を超えて、患者さんの人生の最期に関わることを切ないことと捉えず、尊いことだと感じる。
例えば、お母さんが亡くなる前、お子様が成人を迎える時に開けられるようなタイムカプセルを作るなど、残された日々を患者さんが思い切り自分らしく生きられるよう、組織全体でサポートする。私たちは、患者さんのそういう想いを支援したいのです。
苦痛を和らげ、限られた命とどう向き合うかということに、みんなで寄り添っていきたいと思っています」
――在宅医療で奮闘する中、先生ご自身も進行がんを患われたそうですが、つらい経験を経て、何か変化はありましたか。
「医師というのは、“こんな検査や治療ができるようになった”と、どうしても技術ばかりに目がいって、ちょっと上から目線で当事者の気持ちを忘れがちになってしまうと思うんですよね。
自分の身に降りかからないとそういう気持ちになれないのかといったらそうではないのですが、実際に父を亡くし、47歳の時に自分自身が病気になったことで、患者さんの気持ちがより深く分かるようになったと思います。
私ががんになった時、子どもはまだ高校生でした。“クリニックをどうしよう。なぜこんな若くしてがんになるんだろう”と、本当の意味で患者さんやご家族の気持ちがより理解できるようになりました」

後悔しない看取り…家族と患者がすべきこと
――本人が在宅医療を希望しても、家族が受け入れに難色を示すケースもあると思います。家族側の心得について、何かいいアドバイスはありますか。
「一番大切なのは、“本人の意思を尊重すること”です。もちろんできないこともあるかもしれませんが、本人にとっての最善は何か、そこに想いを馳せて考えることが大切です。
老老介護や独居でも、私たちで看取ることは可能です。そして患者さんやご家族の皆様に、いつも伝えているのは以下の3つです。
1.本人や家族が自宅で最期を迎えたいと望んでいるかどうか
2.医療は最小限でいいかどうか
3.最期の瞬間を必ずしも看取らなくてもいい
これらをしっかりと理解していれば、我々のサービスが入っていけます。“親の最期の瞬間を看取ることができなかった…”と後悔し、ずっと引きずってしまう方もいると思いますが、過去は変えられないとしても、その後悔や経験を、今後の自分の生き方や家族の看取りに生かすことはできますよね。そう考えると、ちょっとは気持ちが楽になるのかなと。
そして看取れなかったという事実よりも、“それまで自分がどう関わったのか”“本人が楽に生きられたのか”、これが一番大切だということを理解してほしい。
人は必ず死を迎えます。それを避けることはできません。死と向き合うか、向き合わないかでその人の選択肢や人生の終わり方が大きく変わってくると思います」
―― では逆に、患者さん側が家族に対して配慮することは?
「最終的には自分の身を託すことになるので、病気などの事実をありのまま家族に話しておくことでしょうか。また、遠慮をして自分の希望を伝えないままだと、家族は最善の選択ができなくなってしまいます。ご自身の意向をしっかりと伝えておくことが必要です。また、本人が強く望めば、最終的に独居でも看取ることはできるので、家族の負担を考えて在宅医療に切り替えられないなど、自分の希望を諦める必要はないと思います」
幸せだと思える最期とは
――先生が考える「幸せだった」と思える最期とは?
「幸せだと感じるかどうかは、個人によって違うと思います。ただ、死に向き合い、限られた命をどう生きるかを考え、自分らしく人生をやりきったと思えれば、“幸せなさよならだった”と言えるのではないでしょうか」
――本を読んで、エンディングノートを書いてみようと思いました。書くことに前向きではない人に、どのようにアドバイスしたらいいのでしょう。
「まず、エンディングノートをすべて埋める必要はありません。本の中で記した“もしもシート”のように、その日の気分で思いついたことを少しずつ書くだけでいいのです。医療に対する希望も、書いたことは後から気が変わっても全然いいんですよ。
もう一つ、本の中で“人生会議”という項目がありますが、延命治療するとかそういう難しいことではなく、“自分が何を大切に思って生きているのか、何が好きで何が嫌いなのか”を話すだけでもいいと思います。若くても、元気でも、死について話すことは大切で、目的は自分自身で考えることにある。
例えば、身近な人や著名人の死に直面した時、“自分はこうしたいけど、お父さんとお母さんはどう?”など、そういうことから少しずつ話していければいいのではないでしょうか」
――50歳を過ぎると、友人同士で死について話す機会も。しかしどうしても、暗い話になりがちです。もっと前向きに話すためのアドバイスはありますか。
「私の講演会でも、よく“ピンピンコロリで亡くなりたいか、介護を受けて亡くなりたいか”という話が出ます。やはり、ピンピンコロリで亡くなりたいという方が多く、大多数の方が手を挙げますが、さらに“明日亡くなってもいいと思えますか?”と聞くと、すーっと手が下がるんですよね。
そんな中、わずか数パーセント“ピンピンコロリであれば、明日亡くなってもいい”という方がいます。話を聞くと“私はやりたいことをやってきた。だから今日亡くなっても悔いはない”とおっしゃる。ただ長く生きるのではなく、“自分らしくいつ死んでもいい”と思える人たちがいる…これはすごいことだなと。
例えばですが、そこに向かって、自分らしくやりたいことをやりきる、死に向き合うという話は、非常に前向きですよね。
生き方の選択肢はたくさんあります。友人同士または家族間においても、“最期までこれが食べたい”“家族にこういうことを伝えたい”など、具体的な希望を話してみると、暗くなく前向きな話へと変わるのではないでしょうか。
明日心筋梗塞で亡くなるかもしれないし、事故で亡くなるかもしれない…それはみんな同じです。だからこそ、“あと何年自分に時間があるだろう”と、一度考えてほしい。
今はそういうアプリもありますし、人生の残り時間を意識してみると、意外と短いことに気づきます。その時間をどう使うか、どう社会に貢献するかを考えることが、前向きに死を捉えるきっかけになると思います。
人生会議を大切に…これからの自分や家族のために、一度人生の終わりを考えてみてはいかがでしょうか」
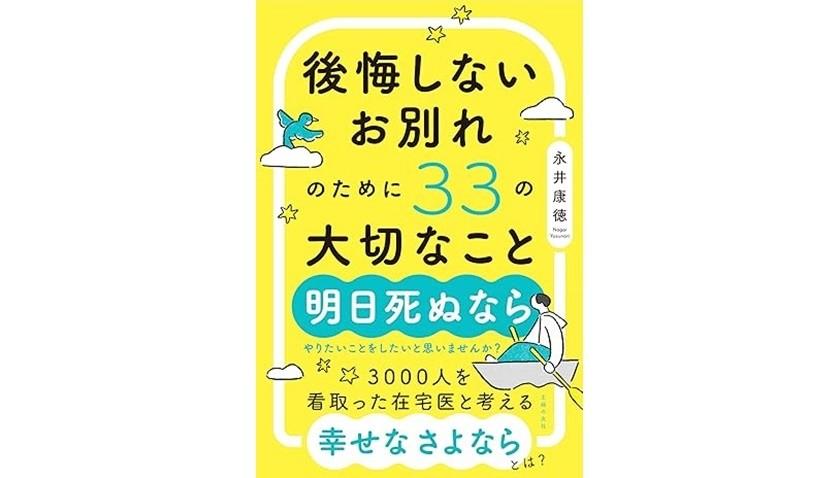 ▲『後悔しないお別れのために33の大切なこと』(主婦の友社)
▲『後悔しないお別れのために33の大切なこと』(主婦の友社)【永井康徳 プロフィール】

医療法人ゆうの森 たんぽぽクリニック 医師
愛媛県のへき地診療所勤務の後、2000年に愛媛県松山市で、四国で初めての在宅医療専門のたんぽぽクリニックを開業。
「理念」と「システム」と「人材」のすべてを高いレベルで維持して在宅医療の質を高めることをめざし、現在は常勤医10人、職員100人の多職種チームで在宅医療を主体に、有床診療所、外来の運営も行っている。
平成22年には市町村合併の余波で廃止となった人口約1200人の町の国保へき地診療所を民営化し、開設4ヶ月で黒字化を達成。そのへき地医療への取り組みは平成28年に第1回日本サービス大賞地方創生大臣賞を受賞。全国各地での講演を行い、「全国在宅医療テスト」や「今すぐ役立つ在宅医療未来道場(通称いまみら)」「流石カフェ」など在宅医療の普及のための様々な取り組みを行っている。
コロナ禍で現地講演会が難しくなってからは、YouTubeで「たんぽぽ先生の在宅医療チャンネル」を開始している。
(取材・文/蓮池由美子)
記事提供元:テレ東プラス
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
