iPhoneとAndroid、日本でのシェアが逆転? OS利用者の割合の動向と展望
 イチオシスト
イチオシスト

かつて「iPhone一強」とまで言われた日本のスマートフォン市場。しかし、その牙城が今、静かに、しかし確実に揺らぎ始めています。最新の調査では、OS別シェアでAndroidがiPhoneを逆転したというデータも現れ、市場の潮目が変わりつつあることを示唆しています。
苦戦が囁かれるiPhoneの現状と、多様な戦略で猛追するAndroid陣営の動きを深掘りします。
日本のスマホ市場におけるiPhone人気に大きな陰り?
日本のスマホ市場におけるiPhone人気は、世界的に見ても特異な現象でした。しかし、その状況が今変化しています。
たとえばMMD研究所が2025年10月に発表した「2025年9月スマートフォンOSシェア調査」の結果によると、メインで利用しているスマホのOSシェアはiPhoneは48.3%、Androidは51.4%とのこと。
さらにメイン利用の通信サービスはiPhone利用率はSoftBankが62.8%、Android利用率は楽天モバイルが60.1%となっており、Android利用者はMVNOを選ぶ傾向があると言えます。
一方、ウェブトラフィックを基にしたStatcounterの調査では、2025年10月時点でiOSのシェアが59.46%、Androidのシェアが40.34%となっています。
なぜ調査によってこれほどの差が生じるのでしょうか。
これは、調査方法の違いが原因です。MMD研究所の調査はアンケートに基づく「利用者の自己申告」であるのに対し、Statcounterは「ウェブへのアクセスに使われたOS」を分析しています。どちらが絶対的に正しいというわけではなく、両方のデータを踏まえると「iPhoneユーザーは依然として多いものの、新規契約や乗り換えの場面でAndroidを選択する人が着実に増え、その差が急速に縮小している」と解釈するのが最も現実に近いと言えそうです。
少なくとも、これまで盤石と見られていたiPhoneのシェアが、もはや安泰ではないことは間違いありません。
iPhoneシェア低下の背景
日本におけるiPhoneのシェア低下には、複数の要因が複雑に絡み合っています。最も大きな要因として挙げられるのが、iPhoneの価格高騰。日本市場の円安や半導体不足により電子機器の価格は上昇し続け、iPhoneも大きな打撃を受けています。

たとえば最新のiPhone 17の価格は256GBモデルで12万9,800円。一方、9年前の2016年に発売されたiPhone 7は当時256GBモデルで9万4,800円となっており、約3万5,000円の差があります。
こうした価格の上昇に対してiPhoneが「革新的な機能」や「特定のヘビーユーザーのニーズを強く満たす要素」などを提供できていないことも間違いないでしょう。つまり「価格上昇に対して納得感を持てないユーザーが増えている」ことが推察されます。

実際、2025年9月に発売されたiPhone Airは販売不振がたびたび報じられており、2026年秋に販売が予想されていたiPhone Air 2(仮)も売り上げの伸び悩みを理由に、発売が延期されるとも報じられています。
iPhone Airは「薄型」を売りにした端末。近年、スマホの大型化を嘆くユーザーが多くいたにもかかわらず売り上げが伸び悩んだことから、iPhoneがスマホ市場で苦戦を強いられているのは明らかでしょう。
Apple Intelligenceの「いまいち感」

2025年4月にリリースされたApple Intelligenceの日本語版は、多くのユーザーから「期待外れ」という評価を受けています。Apple Intelligenceは、いわゆる大規模な対話型生成AIではなく、iPhoneなどのApple製デバイスをより快適に便利に使うためのアシスタント機能に特化しています。
今や「AI」と言えば、ChatGPTやGoogleのGeminiといった既存の対話型生成AI。しかし、実際のApple Intelligenceはそれらと比較して物足りなさを感じさせる場面が多く、「できることが限られている」「他社の生成AIはもっといろいろなことができる」といった声が聞かれることに。そのため、Apple Intelligenceにはどうしても“いまいち感”が残る形となりました。
それでもなおAppleは今後、生成AIを組み込んだ「Apple Intelligence」で巻き返しを図ると見られていますが、Android陣営もGoogleを中心にAI機能の強化を進めており、競争はさらに激化するでしょう。
Androidの三つの成長要因
iPhoneが苦戦を強いられた一方、Androidが成長できた要因としては、低価格帯の端末が多いこと、一方ではハイエンドスマホも充実していること、さらにヘビーユーザーの要求に応える機能が豊富であることが挙げられます。
低価格帯の端末
Android端末の最大の強みのひとつは、豊富な低価格帯ラインナップです。1万円台から購入できるエントリーモデルから、5万円前後のミドルレンジまで、消費者の予算に応じた幅広い選択肢が用意されています。
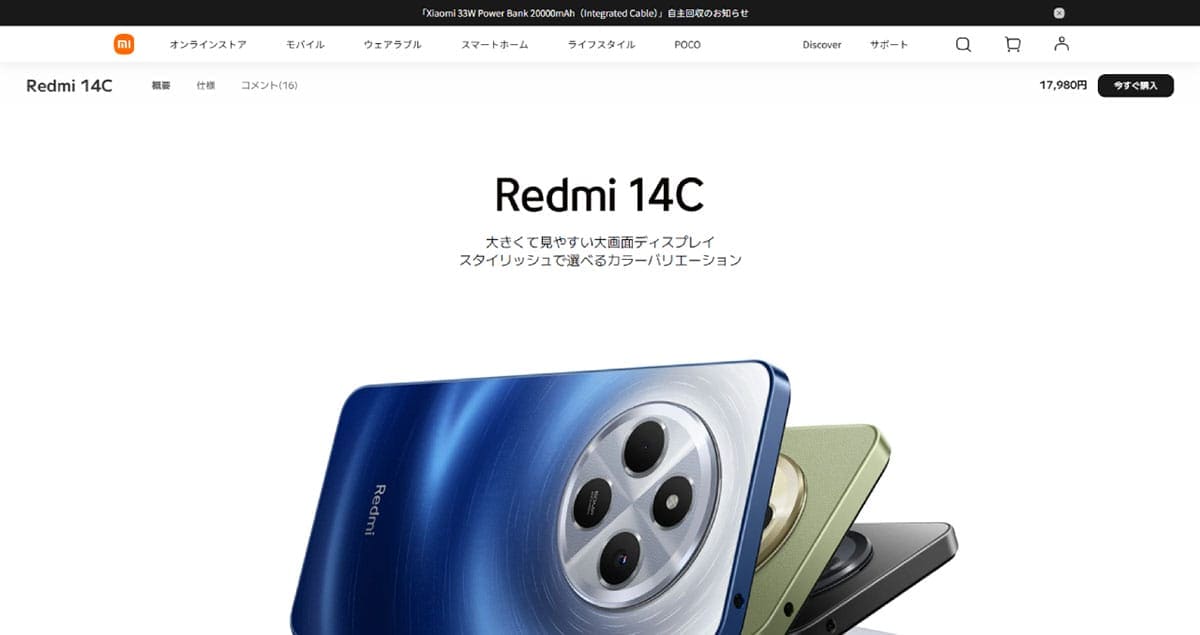
たとえば一部海外モデルのエントリーモデル~ミドルレンジ帯のAndroidスマホではおサイフケータイ(FeliCa)非対応の機種も増えています。たとえおサイフケータイに対応していなくてもPayPayなどのQRコード決済が普及した今、代替の決済手段を探すことは難しくありません。
FeliCaの技術使用料を支払う必要がないので端末自体の価格も下げることができ、ユーザーの支持を得ています。
Xiaomi 15 Ultraに代表される『ハイエンド』への進出

低価格帯での強みに加えて、Android陣営はハイエンド市場でも目覚ましい進化を遂げています。その象徴的な存在がXiaomi 15 Ultraです。Xiaomi 15 Ultraは、最新のSnapdragon 8 Elite Mobile Platformを搭載し、前世代と比較してCPU・GPU及びAI処理性能が大幅に向上しています。
Xiaomi 15 Ultraはライカと共同開発したクアッドカメラシステムで、1インチのイメージセンサーを搭載したメインカメラと2億画素の望遠カメラにより、スマートフォンカメラの最高峰と評される性能を実現しています。
このようなハイエンドモデルの充実により、Androidは、かつての「安かろう悪かろう」という評価を完全に払拭し、iPhoneに匹敵する、あるいは特定の機能においては上回る選択肢として認知されるようになっています。
特定のヘビーユーザーの要求に応える機能の提供

Android端末のもう一つの大きな強みは、ヘビーユーザーの多様でマニアックな要求に応える機能の幅広さです。たとえば注目される機能の一つが、バイパス給電(ダイレクト給電)です。
バイパス給電とは、充電器からの電力をバッテリーを経由させず、本体に直接供給する仕組みのことです。従来の充電方式では、充電器からの電力がバッテリーを経由してスマートフォン本体に供給されるため、バッテリーが継続的に充放電を繰り返すことになり、これが長期的なバッテリー劣化の一因となっています。バイパス給電では、バッテリーを完全に電力供給回路から切り離すことで、不要な負荷を軽減し、バッテリーの発熱や劣化を大幅に抑制することができるのです。
一方、iPhoneはバイパス給電機能を搭載していません。iPhoneはQi規格に基づくワイヤレス充電に対応していますが、Qi規格では最大7.5ワットの給電となります(MagSafe使用時は機種により最大15~25ワット)。いずれの充電方法でも、バッテリーを迂回して直接本体に電力を供給する機能は実装されていません。
バイパス給電はあくまで一例ですが、特定のヘビーユーザーの要求に応える機能の提供という面で、Androidが一歩先を行く場面も増えています。ゲーマーやクリエイターなど、スマホを本格的な仕事用デバイスとして活用するユーザーにとって、これらの専門的なニーズに応える機能の充実度は、購買決定に大きく影響する重要な要素となっているのです。
Android端末は、低価格帯での充実、ハイエンド市場での競争力強化、そしてヘビーユーザーのニーズへの対応という三つの成長要因により、日本市場においても着実にシェアを拡大していると言えるでしょう。
※サムネイル画像(Image:Shutterstock.com)
記事提供元:スマホライフPLUS
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
