意外と知らない、「Arm版Windows」は普通のWindowsパソコンと何が違うのか?
 イチオシスト
イチオシスト

新しいノートパソコンを選びに家電量販店へ足を運んだり、オンラインストアを眺めたりしていると、「Surface Pro(Arm版)」といった言葉を目にすることが増えてきました。多くの人が慣れ親しんだ「Intel Core」や「AMD Ryzen」搭載の普通のパソコンと、この「Arm版」はいったい何が違うのでしょうか?
「Windowsはどれも同じじゃないの?」と思うかもしれません。しかし、この「Arm版Windows」は、これまでのパソコンの常識を少し変えるかもしれない、大きな可能性と、同時に無視できない課題を抱えた存在です。詳しく見ていきましょう。
省エネな「Arm」とパワフルな「x86」

Arm版Windowsとは、主にスマートフォンやタブレットで利用されているArmアーキテクチャを搭載したCPU上で動作するWindowsの一種です。従来のx86やx64アーキテクチャとは異なり、省エネで効率良く動作する点が特徴で、「持ち運びやすいWindows」とも言える存在。そのため、モバイル端末向けとして開発されています。
最大の違いは、パソコンの「心臓部」にあたるCPU(プロセッサー)の設計思想、すなわちアーキテクチャが根本的に異なる点にあります。
スマートフォンの多くに搭載されているのがArmアーキテクチャです。これは「RISC(リスク)」という考え方で作られており、「シンプルな命令を高速に大量処理する」のが得意です。その結果、消費電力が少なく、バッテリーが長持ちします。Armの際立った特徴は、この高い電力効率にあります。
一方、従来のWindowsパソコンで主流だったIntelやAMDのCPUはx86アーキテクチャ(CISC方式)を採用しています。「複雑な命令を一度にこなす」ことで高性能を発揮しますが、その分消費電力も大きくなる傾向がありました。
Armアーキテクチャは以前から存在していましたが、パソコン市場では長らくx86が主流でした。この流れを変えたのが、2020年にAppleが自社開発のArmベースチップ「M1」をMacに搭載したことです。これにより「省エネかつ高性能」というArmの新しいイメージが定着しました。
この成功を受け、Windowsの世界でもArm化が加速。MicrosoftとQualcommが共同で、x86に匹敵または凌駕するArmチップを開発したことが現在の盛り上がりにつながっています。
Arm版Windowsのメリットとは?
Arm版Windows PCの最大の魅力は、スマートフォンに近い使い勝手です。消費電力が少ないため、一度の充電で一日中使えるモデルも珍しくありません。カフェや移動中にコンセントを探すストレスから解放されます。
加えて発熱が少ないため、冷却ファンを搭載しない「ファンレス」設計の機種が多くあります。そのため、図書館のような静かな場所でも、ファンの音を気にせず作業に集中できます。
Arm版Windowsのデメリットとは?
Arm版Windowsの歴史は「アプリ互換性との戦い」でもありました。
Intel向けアプリにはx86(32bit)版とx64(64bit)版があります。x86(32bit)版は比較的問題なく動きますが、x64(64bit)版はArm版Windows 11ではエミュレーション経由のため動作が遅くなることがあります。また、32bit版アプリは配布終了が進んでおり入手困難な場合もあります。
そしてx86(32bit)アプリはサポートの打ち切りなどが目立つのも現状です。目当てのソフトウェアのx86(32bit)向けインストーラーの配布状況が分からず「64bitのインストーラーならすぐ見つかるのに、32bitのインストーラーを探すのに時間が掛かるのはあまりに無駄だ」と感じたことがある方は少なくないのでは?
もっとも2025年現在のWindows 11 on Armは「エミュレーション」という翻訳機能を持ち、従来のx86/x64アプリも動かせます。しかし、この機能は万能ではありません。動かない、あるいは利用に重大な制限があるアプリの存在が、特に日本市場での普及を阻む大きな要因となっています。
たとえばプリンターやスキャナー、オーディオインターフェースなど、メーカーがArm用ドライバーを提供していない場合、その機器は使えません。ネイティブドライバーが必要なアプリや機能は、非互換の問題が発生しやすいです。
ATOKの非対応

日本で特に深刻なのが、ジャストシステムの日本語入力ソフト「ATOK」の互換性です。ATOKはArm版Windowsにインストールはできるものの、完全にArmネイティブで動作するアプリ(例:新しいファイルエクスプローラーなど)上では日本語入力ができません。これは、執筆業や特定の業務でATOKが必須なユーザーにとって致命的な問題です。ATOKの公式サイトでも「Arm版Windowsは動作保証外です」と明記されています。
なお動作保証外のソフトウェアをエミュレーションによって、自己責任で動かすこと自体は不可能ではないでしょう。しかしエミュレーションで動くアプリの速度は1~2世代前のプロセッサー程度であり、ネイティブアプリほどの快適さは期待できません。
非対応のゲームタイトルが極めて多い
Arm版WindowsはDirectX 12を使用するx86アプリをエミュレーション経由でサポートしています。OpenGLについては、ネイティブではOpenGL 1.1までの制限がありますが、Microsoft提供の互換パックによりOpenGL 3.3まで対応可能です。互換パックなしでは、OpenGL 1.1以降を使用するゲームは動作しません。
また、アンチチートシステムがARMアーキテクチャに「対応しているかどうか」によっても、目当てのゲームが遊べるかどうかが左右されます。そのため、たとえば「Apex Legends」や「PUBG: Battlegrounds」といった人気タイトルは動作しませんでした。
一方、「フォートナイト」もこれまではArm版Windowsでプレイすることはできませんでしたが、2025年3月にEpic GamesがQualcommと協力してWindows on Snapdragon対応とフォートナイト対応を発表。2025年後半に実装される予定です。
このように、Arm版Windowsの需要が高まることでメーカー側が対応するケースもあるとは言えるでしょう。
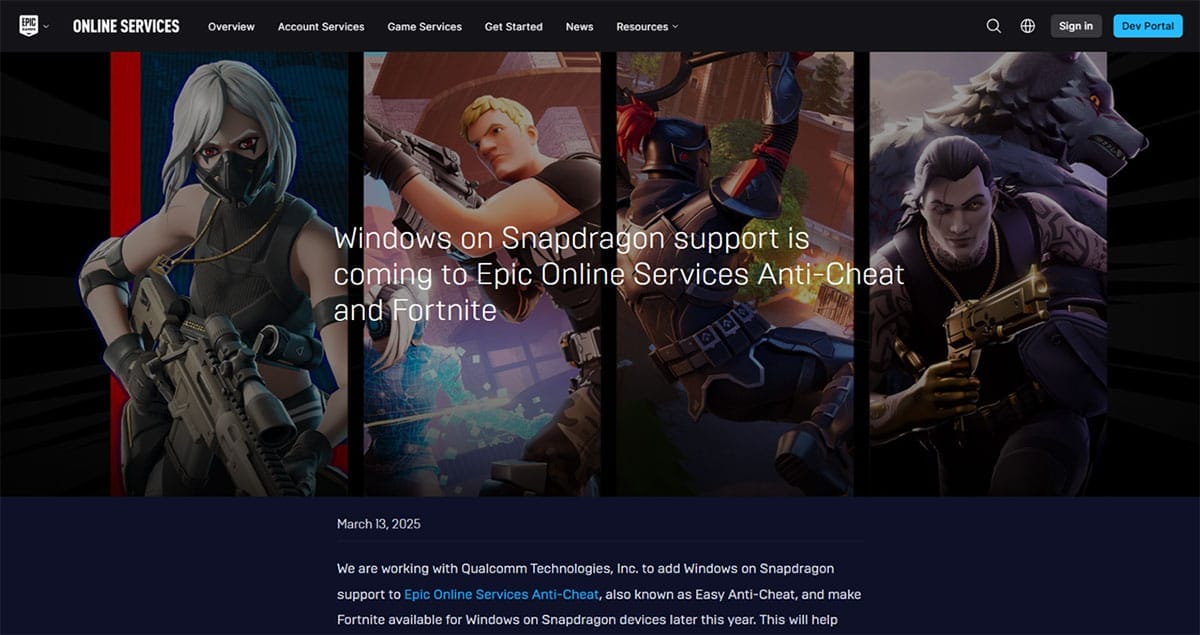
大学でも非推奨のケースが多い
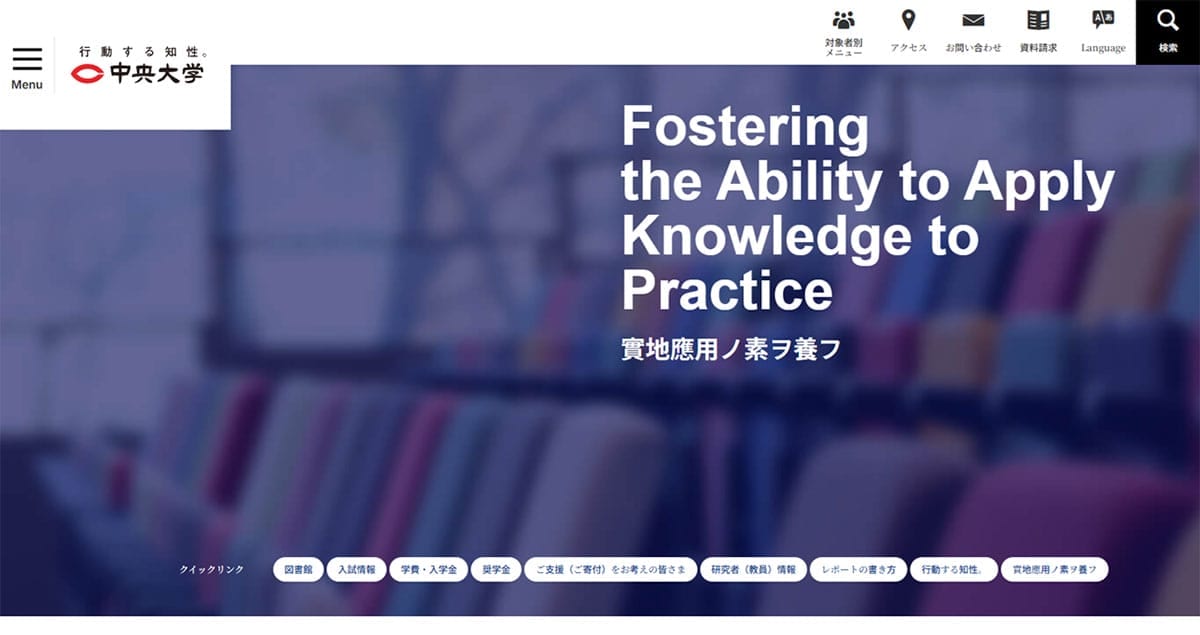
互換性問題は、個人ユーザーだけでなく、教育機関や企業にとっても大きな懸念事項です。そのため、多くの大学が学生に対し、Arm版Windows PCの購入に注意を促しています。
中央大学は、統計ソフト「SPSS」「AMOS」や、学内のオンデマンドプリンター用ドライバーがArm版Windowsで利用できないことを理由に、学生へ注意喚起を行っています。そして「ソフトウェアがインストールできない等の問題については、ご自身の責任で対処いただくことになります」と明記し、IntelまたはAMD製CPU搭載機種の選定を推奨しています。
ArmアーキテクチャのPCを求めるならMacへの乗り換えがおすすめ?
Appleが2020年以降、Armアーキテクチャに移行して大きな成功を与えたことはPC業界に衝撃を与えました。
そこでMicrosoftと長年のパートナーであるQualcommは、PC向けArmチップ「Snapdragon X Elite」および「Snapdragon X Plus」を開発しました。これらのチップは、CPU性能でAppleやIntelの現行チップを上回ることを目標に掲げています。こうした動向を基に、2020年代の終わりごろまでにWindows市場でもArmアーキテクチャが支配的なシェアを獲得するという見立てもあります。
Armアーキテクチャが「省エネなのに、ものすごく高性能」なのは事実であり、個人・法人で利用するWindowsがすべてArmアーキテクチャに置き換わった場合、バッテリー持ちや電力効率の面で極めて大きな変化にもなるでしょう。
もっとも本稿の中で触れた通り、Arm版Windowsは将来性こそあるものの難もあり、少なくとも一般ユーザーが安心して使える段階には遠いです。事前に「普通のWindows」と「Arm版Windows」の違いを知らなければ、PCを買った後に「なぜかATOKが動かない」「なぜか大学で必要なソフトウェアが動かない」などトラブルの原因にすらなるでしょう。
Armアーキテクチャにおいて市場で先行しているのはAppleであることも事実です。Armアーキテクチャの端末を求めるならば、WindowsではなくMacを選ぶのも一案です。もしWindowsにこだわりがあり、なおかつ必要なアプリの互換性に少しでも不安があるなら、今はまだ従来のx86版PCを選ぶのが最も安全で確実な選択と言えるでしょう。
※サムネイル画像(Image:Shutterstock.com)
記事提供元:スマホライフPLUS
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
