「日本画」を愛する外国人が感涙…新鋭画家から伝統技法を学ぶ:世界!ニッポン行きたい人応援団
更新日:
 イチオシスト
イチオシスト
ライター / 編集
イチオシ編集部 旬ニュース担当
注目の旬ニュースを編集部員が発信!「イチオシ」は株式会社オールアバウトが株式会社NTTドコモと共同で開設したレコメンドサイト。毎日トレンド情報をお届けしています。
ニッポンに行きたくてたまらない外国人を世界で大捜索! ニッポン愛がスゴすぎる外国人をご招待する「世界!ニッポン行きたい人応援団」(毎週月曜夜8時54分 ※11月17日は夜8時放送)。
今回は、スペインに住む外国人の来日の様子をお届けします。
【動画】「世界!ニッポン行きたい人応援団」最新回
紹介するのは、スペイン在住の「日本画」を愛するイングリディさん。

日本画とは、和紙や絹に岩絵具や胡粉と呼ばれる白い顔料を重ね、膠という天然の接着剤で定着させるなど、ニッポンの伝統的な素材や技法を用いて描かれる絵画。
ニューヨークのメトロポリタン美術館にも所蔵され、世界でも高く評価されています。
そんな日本画を愛してやまないイングリディさんを、ニッポンにご招待!
憧れの日本画家・林 潤一さんの作品をニッポンで見るのが夢だそう。林さんは花木画の名手とされ、今年1月に逝去された日本美術界の巨匠です。

そこで、ウェルカムサプライズ! 京都・嵐山にある林さんのご自宅で作品を鑑賞させていただくことに。作品を目の前にしたイングリディさんは感動! 林さんの妻・靖代さんによると、林さんは年の3分の1を写生に費やしていたとか。
さらに靖代さんから、林さんが生前使用していた筆とデッサン画のプレゼントが。恐縮するイングリディさんに、「本人も喜ぶと思います」と靖代さん。「少しでも林先生に近づけるように日本画を勉強します」と伝えました。
実はイングリディさん、日本画を知ったのは3年前。インターネットで林さんの作品を見つけて一目惚れしたそう。絵を描くことが得意だったこともあり、昨年、日本画の画材を購入して独学で描き始めました。
しかし、画材を正しく使えているか自信がなく、独学にも限界が。日本画の花を上手に描く方法を学び、帰国後に最高傑作を完成させるのが目標です。
そこで、まずはニッポンの白色を作る画材「胡粉」について学ぶことに。
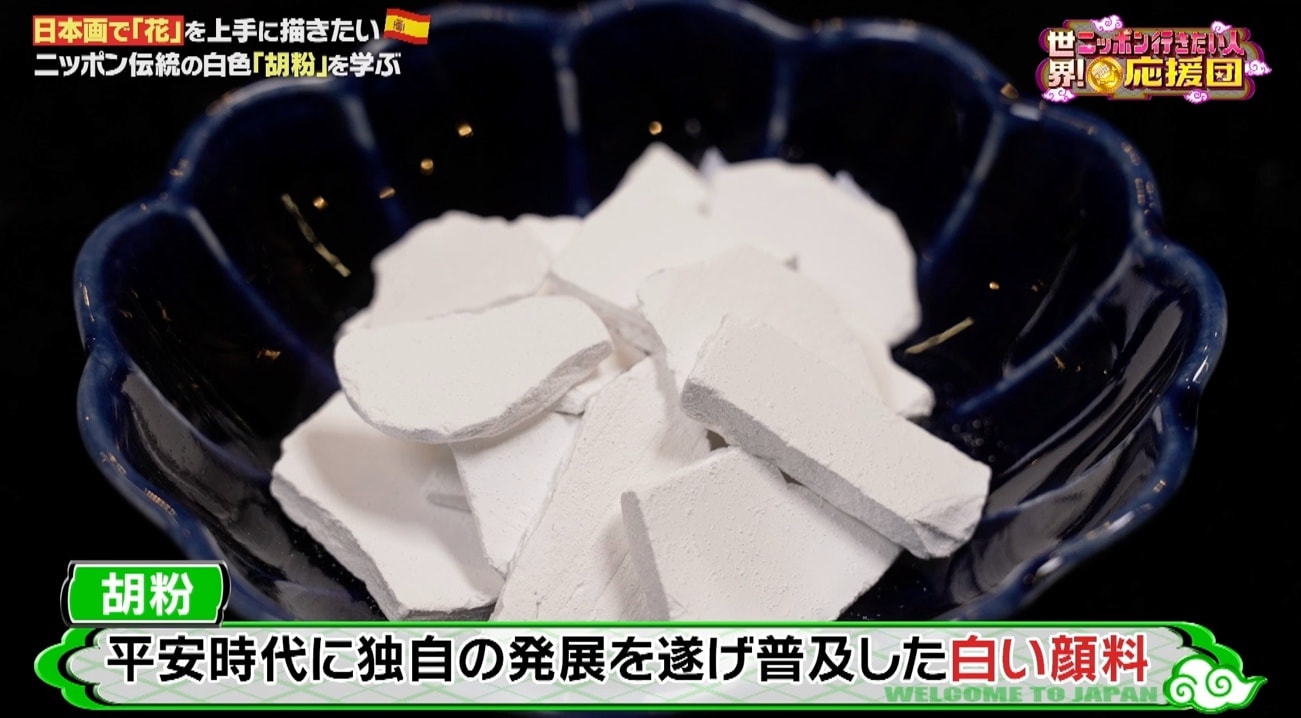
胡粉とは、平安時代に独自の発展を遂げて普及した白い顔料。発色が柔らかく温かみがあり、雛人形の肌色や寺社の装飾にも使われています。
イングリディさんが普段使っている白い顔料は、チューブ状の絵の具。いつか本物の胡粉で花を描くのが夢でした。
今回お世話になるのは、京都府宇治市にある「ナカガワ胡粉絵具」。次期五代目の中川翔太さんに、胡粉がどのように作られているか教えていただきます。
胡粉の原料は、天然の「いたぼ牡蠣」の貝殻。細かく割れやすくするため、20年以上野ざらしにして風化させてから使います。
このいたぼ牡蠣の殻を、上と下に分けてます。真っ白なのは蓋の殻で、身が入っていた殻を混ぜる割合でグレードが変わるそう。100%蓋の殻で作られたものが最高級に!

分けた殻は、60㎏の柱が上下に動く機械で粉々にした後、水を加えて泥状に。さらに石臼で擦りつぶし、滑らかにします。粒をどれだけ砕くかが、白を美しく発色させる大事なポイント。
擦りつぶした殻は、この時点ではまだ灰色ですが、板に薄く伸ばして2週間天日干しをすることで真っ白に。これで胡粉の完成です。
この胡粉を絵の具にする方法を、中川さんの姉・裕季子さんが教えてくださいます。
まずは、胡粉を乳鉢で擦ります。ザラザラが残っている状態では良い絵の具にならないそう。

粉状になったら、胡粉と膠を練り合わせて胡粉団子を作ります。膠とは、動物の皮膚や骨から抽出される天然の接着剤で、胡粉に少しずつ膠を加えて団子にしたら、お皿に叩きつけます。これは、「百叩き」という工程で、百回叩くことで胡粉と膠が馴染み、発色が良くなります。
叩いた胡粉団子を膠と水で溶かせば、白色の絵の具が完成。黒い紙に試し描きをさせていただき、「これがニッポン伝統の白色なんですね」とイングリディさん。
最後に中川さんから、帰ったらすぐ描けるようにと胡粉や乳鉢、膠のセットをいただき、大喜びで「大切に使います」と伝えました。
「ナカガワ胡粉絵具」の皆さん、本当にありがとうございました!
続いて、埼玉県草加市へ。金箔や銀箔を用いて表現する日本画の手法を学ばせていただくため、創業101年「菊池襖紙工場」へ。
こちらでは、襖紙や壁紙の製造に加え、職人が手作業で金銀細工も施しています。
中でも金銀砂子師は、平安時代から続く金銀の装飾技法を使う工芸職人。どのように細工を施すのか、砂子師の山本和久さん、青柳奈央子さんに見せていただくことに。
イングリディさんは、実物の金箔を見るのは初めて。薄い金箔は手で触るとくっついてしまうため、箔箸で掴みます。

金箔を砂子筒に入れ、トング状の打ち棒で叩くと、下の網から砂状の金箔が。砂子筒の中には馬の尻尾の毛を針金で束ねた「踊り子」が入っており、筒を叩いた時に中の踊り子が激しく動き、金箔を細かくしています。これが、伝統技法の「砂子」。
砂子技法には、金箔を小さく裁断した「切り箔」や、細かい線状の「野毛」も使われ、砂子師の手作業で作られます。竹刀という刃物を優しく押し当て、四角に切り揃えれば切り箔に。今回、山本さんが作った切り箔は一辺わずか6㎜。野毛はなんと0.05㎜幅と、その緻密さにイングリディさんは驚き!
いよいよ砂子技法に挑戦させていただきます。まずは、砂子筒に金箔を入れて砂状に。砂子を出す量は打ち棒で叩くスピードにより調節するそうで、「難しいですね」とイングリディさん。

続いて、切り箔。極薄の金箔を15㎜間隔で裁断します。緊張しながら進めますが…笑った息で金箔が飛んでしまうハプニングが!
「いい感じだったのに」と悔しがるイングリディさん、今度は息を殺して慎重に作業し、切り箔作りが終了。山本さんは「日本人でもなかなかここまで上手に切れません」と褒めてくださいました。
ここで「花を描く上で砂子細工をどのように使えば良いか」と質問。山本さんは、砂子を撒いて風景に奥行き感を出しているそうで、細工を施した花の襖画を見せてくださいました。「とても雰囲気が出ています!」(イングリディさん)。
最後に、金銀砂子細工の道具一式をいただき大感激! 「砂子を使った日本画を仕上げて、必ずここに持ってきます」と伝えました。
「菊池襖紙工場」の皆さん、本当にありがとうございました!
続いて向かったのは、東京・世田谷。日本画家・日月美輪さんのアトリエにやって来ました。四季の花を題材にしている日月さんは、数々の受賞歴がある今注目の若手作家。
そしてなんと、イングリディさんが憧れる林 潤一さんに教わったことも。
今回は、花を上手に描く技を教えていただきます。
日本画のプロが多く使っているのは、岩絵具。色がついた鉱石を粒子にした、日本画で一番格式の高い顔料です。
粒子の大きさと色の濃さによって番号で分けられ、粒子が細かく一番薄い色のものは白(びゃく)と呼ばれています。イングリディさんは昨年、画材店で岩絵具を見つけたものの、使い方が分からなかったそう。

岩絵具は、膠と水に溶いて使用します。水彩絵具のように紙に染み込むのではなく、顔料を表面に乗せて着色。色を重ねることで、立体的な表現が可能に。「使うのも難しいですけど、もっと表現の幅が増える」と日月さん。
どのように色を重ねて表現するのか、下書きしたユリの花の色付けを見せていただきます。まずは花のベースから。岩絵具の番号が大きい、色が薄いものから描いていくと、絵の具が安定して乗りやすいそう。しっかり乾かして重ねることも大切です。
花びらのグラデーションは「ぼかし」で表現。彩色筆で岩絵具をつけた部分を、水を含ませた隈取筆でなぞれば、柔らかな濃淡に。イングリディさんも同じ方法で描いていましたが「先生の色彩は特別です」と話します。

花びらの周りは、胡粉をぼかして彩色し、可憐な花びらに。さらに、固めに溶いた胡粉を、しべと花脈の部分に乗せます。これは「盛り上げ」という、胡粉などを重ねて形を立ち上がらせ、立体感や存在感を出す手法です。
こうして重ね塗りされた岩絵具はほのかに煌めき、花脈としべはその姿を際立たせ、胡粉の白が花びらを柔らかく引き立てています。イングリディさんは「完璧な美しさです」と絶賛。
たくさんの技法を教えていただいた感謝を伝えると、日月さんから日本画の作者の証である「落款」のプレゼントが。「帰国してすぐ日本画を描いて、これを押して完成させます」と喜ぶイングリディさんでした。
日月さん、本当にありがとうございました!
帰国後、滞在中に学んだことを活かし、花の日本画の制作に取りかかったイングリディさん。

完成品を見せてもらうと、背景には金箔砂子が煌めき、岩絵具で深みのある質感に。胡粉で描いた花びらは、ぼかしの手法で奥行きを表現。以前と比べ、より洗練されて完成度が高い仕上がりになっています。
実は、日月さんからいただいた落款も押したのですが、配色ミスで背景に埋もれてしまったそう。「先生ごめんなさい、それ以外は最高傑作だと自負しています」と語ってくれました。
イングリディさん、またの来日をお待ちしています!
月曜夜8時からは「世界!ニッポン行きたい人応援団」を放送!
▼大工をしていたピーターさんはSNSで見つけた日本の漆器に魅了され、以来独学で漆器を作り続けていた。漆塗り職人のもとで本格的に技術を学ぶのが夢だという。
▼2023年6月、漆のすべてを学ぶために日本を代表する漆器の産地、石川県輪島市へ!
江戸末期に創業した「大﨑漆器店」には1000点もの輪島塗の漆器が展示されているギャラリーがあり、人間国宝の作品などに触れて大感動する。
▼お椀の木地作り、漆の採取、漆塗り、磨きなど、各工程は分業制になっている。それぞれの専門の職人から美しく繊細な技を教えてもらい、本物の漆器作りに初挑戦する。
▼帰国後、教えてもらった技術を駆使してオリジナルの漆器作りに励むピーターさんに、能登半島地震の悲報が舞い込む。お世話になった方々にもう一度会いたいと、震災から2年の時を経て、再来日を果たす。しかし、目の当たりにした光景は想定外のものだった…。
今回は、スペインに住む外国人の来日の様子をお届けします。
【動画】「世界!ニッポン行きたい人応援団」最新回
憧れの巨匠の作品に涙…「胡粉」について学ぶ
紹介するのは、スペイン在住の「日本画」を愛するイングリディさん。

日本画とは、和紙や絹に岩絵具や胡粉と呼ばれる白い顔料を重ね、膠という天然の接着剤で定着させるなど、ニッポンの伝統的な素材や技法を用いて描かれる絵画。
ニューヨークのメトロポリタン美術館にも所蔵され、世界でも高く評価されています。
そんな日本画を愛してやまないイングリディさんを、ニッポンにご招待!
憧れの日本画家・林 潤一さんの作品をニッポンで見るのが夢だそう。林さんは花木画の名手とされ、今年1月に逝去された日本美術界の巨匠です。

そこで、ウェルカムサプライズ! 京都・嵐山にある林さんのご自宅で作品を鑑賞させていただくことに。作品を目の前にしたイングリディさんは感動! 林さんの妻・靖代さんによると、林さんは年の3分の1を写生に費やしていたとか。
さらに靖代さんから、林さんが生前使用していた筆とデッサン画のプレゼントが。恐縮するイングリディさんに、「本人も喜ぶと思います」と靖代さん。「少しでも林先生に近づけるように日本画を勉強します」と伝えました。
実はイングリディさん、日本画を知ったのは3年前。インターネットで林さんの作品を見つけて一目惚れしたそう。絵を描くことが得意だったこともあり、昨年、日本画の画材を購入して独学で描き始めました。
しかし、画材を正しく使えているか自信がなく、独学にも限界が。日本画の花を上手に描く方法を学び、帰国後に最高傑作を完成させるのが目標です。
そこで、まずはニッポンの白色を作る画材「胡粉」について学ぶことに。
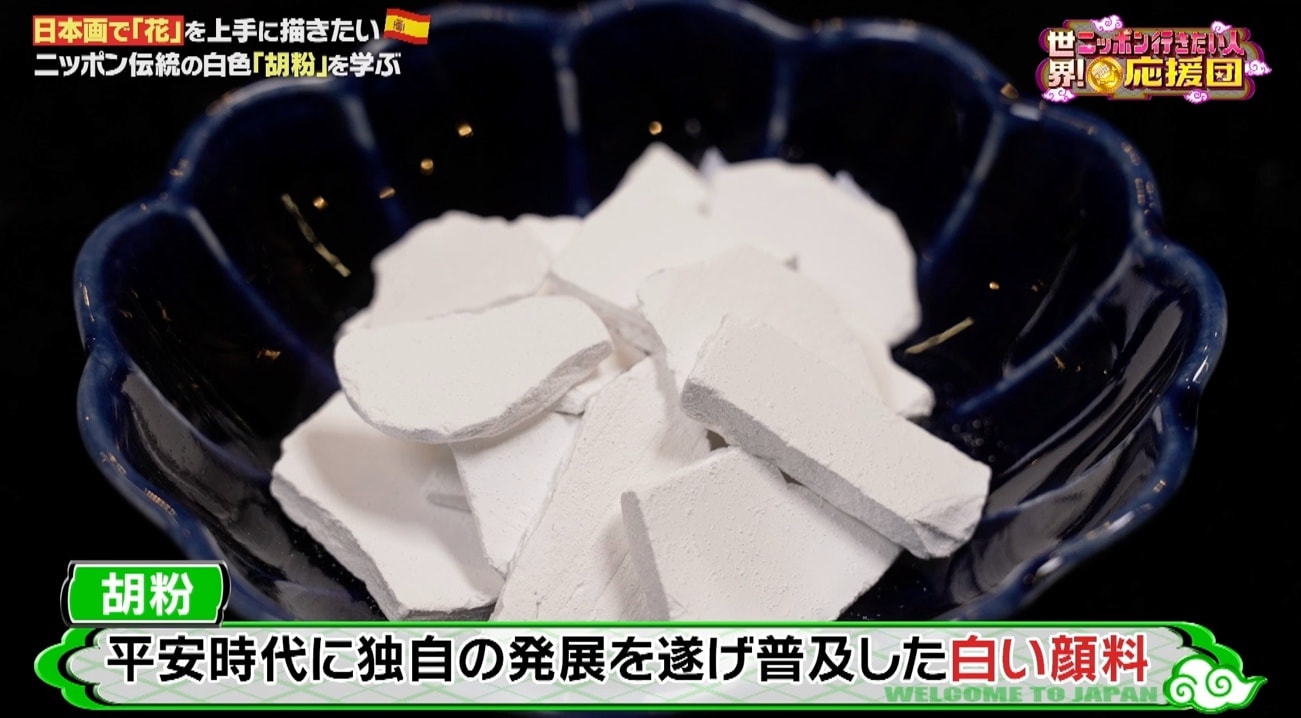
胡粉とは、平安時代に独自の発展を遂げて普及した白い顔料。発色が柔らかく温かみがあり、雛人形の肌色や寺社の装飾にも使われています。
イングリディさんが普段使っている白い顔料は、チューブ状の絵の具。いつか本物の胡粉で花を描くのが夢でした。
今回お世話になるのは、京都府宇治市にある「ナカガワ胡粉絵具」。次期五代目の中川翔太さんに、胡粉がどのように作られているか教えていただきます。
胡粉の原料は、天然の「いたぼ牡蠣」の貝殻。細かく割れやすくするため、20年以上野ざらしにして風化させてから使います。
このいたぼ牡蠣の殻を、上と下に分けてます。真っ白なのは蓋の殻で、身が入っていた殻を混ぜる割合でグレードが変わるそう。100%蓋の殻で作られたものが最高級に!

分けた殻は、60㎏の柱が上下に動く機械で粉々にした後、水を加えて泥状に。さらに石臼で擦りつぶし、滑らかにします。粒をどれだけ砕くかが、白を美しく発色させる大事なポイント。
擦りつぶした殻は、この時点ではまだ灰色ですが、板に薄く伸ばして2週間天日干しをすることで真っ白に。これで胡粉の完成です。
この胡粉を絵の具にする方法を、中川さんの姉・裕季子さんが教えてくださいます。
まずは、胡粉を乳鉢で擦ります。ザラザラが残っている状態では良い絵の具にならないそう。

粉状になったら、胡粉と膠を練り合わせて胡粉団子を作ります。膠とは、動物の皮膚や骨から抽出される天然の接着剤で、胡粉に少しずつ膠を加えて団子にしたら、お皿に叩きつけます。これは、「百叩き」という工程で、百回叩くことで胡粉と膠が馴染み、発色が良くなります。
叩いた胡粉団子を膠と水で溶かせば、白色の絵の具が完成。黒い紙に試し描きをさせていただき、「これがニッポン伝統の白色なんですね」とイングリディさん。
最後に中川さんから、帰ったらすぐ描けるようにと胡粉や乳鉢、膠のセットをいただき、大喜びで「大切に使います」と伝えました。
「ナカガワ胡粉絵具」の皆さん、本当にありがとうございました!
伝統の金銀装飾技法「砂子」を体験
続いて、埼玉県草加市へ。金箔や銀箔を用いて表現する日本画の手法を学ばせていただくため、創業101年「菊池襖紙工場」へ。
こちらでは、襖紙や壁紙の製造に加え、職人が手作業で金銀細工も施しています。
中でも金銀砂子師は、平安時代から続く金銀の装飾技法を使う工芸職人。どのように細工を施すのか、砂子師の山本和久さん、青柳奈央子さんに見せていただくことに。
イングリディさんは、実物の金箔を見るのは初めて。薄い金箔は手で触るとくっついてしまうため、箔箸で掴みます。

金箔を砂子筒に入れ、トング状の打ち棒で叩くと、下の網から砂状の金箔が。砂子筒の中には馬の尻尾の毛を針金で束ねた「踊り子」が入っており、筒を叩いた時に中の踊り子が激しく動き、金箔を細かくしています。これが、伝統技法の「砂子」。
砂子技法には、金箔を小さく裁断した「切り箔」や、細かい線状の「野毛」も使われ、砂子師の手作業で作られます。竹刀という刃物を優しく押し当て、四角に切り揃えれば切り箔に。今回、山本さんが作った切り箔は一辺わずか6㎜。野毛はなんと0.05㎜幅と、その緻密さにイングリディさんは驚き!
いよいよ砂子技法に挑戦させていただきます。まずは、砂子筒に金箔を入れて砂状に。砂子を出す量は打ち棒で叩くスピードにより調節するそうで、「難しいですね」とイングリディさん。

続いて、切り箔。極薄の金箔を15㎜間隔で裁断します。緊張しながら進めますが…笑った息で金箔が飛んでしまうハプニングが!
「いい感じだったのに」と悔しがるイングリディさん、今度は息を殺して慎重に作業し、切り箔作りが終了。山本さんは「日本人でもなかなかここまで上手に切れません」と褒めてくださいました。
ここで「花を描く上で砂子細工をどのように使えば良いか」と質問。山本さんは、砂子を撒いて風景に奥行き感を出しているそうで、細工を施した花の襖画を見せてくださいました。「とても雰囲気が出ています!」(イングリディさん)。
最後に、金銀砂子細工の道具一式をいただき大感激! 「砂子を使った日本画を仕上げて、必ずここに持ってきます」と伝えました。
「菊池襖紙工場」の皆さん、本当にありがとうございました!
「岩絵具」と重ね塗り 花を上手に描く技法を学ぶ
続いて向かったのは、東京・世田谷。日本画家・日月美輪さんのアトリエにやって来ました。四季の花を題材にしている日月さんは、数々の受賞歴がある今注目の若手作家。
そしてなんと、イングリディさんが憧れる林 潤一さんに教わったことも。
今回は、花を上手に描く技を教えていただきます。
日本画のプロが多く使っているのは、岩絵具。色がついた鉱石を粒子にした、日本画で一番格式の高い顔料です。
粒子の大きさと色の濃さによって番号で分けられ、粒子が細かく一番薄い色のものは白(びゃく)と呼ばれています。イングリディさんは昨年、画材店で岩絵具を見つけたものの、使い方が分からなかったそう。

岩絵具は、膠と水に溶いて使用します。水彩絵具のように紙に染み込むのではなく、顔料を表面に乗せて着色。色を重ねることで、立体的な表現が可能に。「使うのも難しいですけど、もっと表現の幅が増える」と日月さん。
どのように色を重ねて表現するのか、下書きしたユリの花の色付けを見せていただきます。まずは花のベースから。岩絵具の番号が大きい、色が薄いものから描いていくと、絵の具が安定して乗りやすいそう。しっかり乾かして重ねることも大切です。
花びらのグラデーションは「ぼかし」で表現。彩色筆で岩絵具をつけた部分を、水を含ませた隈取筆でなぞれば、柔らかな濃淡に。イングリディさんも同じ方法で描いていましたが「先生の色彩は特別です」と話します。

花びらの周りは、胡粉をぼかして彩色し、可憐な花びらに。さらに、固めに溶いた胡粉を、しべと花脈の部分に乗せます。これは「盛り上げ」という、胡粉などを重ねて形を立ち上がらせ、立体感や存在感を出す手法です。
こうして重ね塗りされた岩絵具はほのかに煌めき、花脈としべはその姿を際立たせ、胡粉の白が花びらを柔らかく引き立てています。イングリディさんは「完璧な美しさです」と絶賛。
たくさんの技法を教えていただいた感謝を伝えると、日月さんから日本画の作者の証である「落款」のプレゼントが。「帰国してすぐ日本画を描いて、これを押して完成させます」と喜ぶイングリディさんでした。
日月さん、本当にありがとうございました!
帰国後、滞在中に学んだことを活かし、花の日本画の制作に取りかかったイングリディさん。

完成品を見せてもらうと、背景には金箔砂子が煌めき、岩絵具で深みのある質感に。胡粉で描いた花びらは、ぼかしの手法で奥行きを表現。以前と比べ、より洗練されて完成度が高い仕上がりになっています。
実は、日月さんからいただいた落款も押したのですが、配色ミスで背景に埋もれてしまったそう。「先生ごめんなさい、それ以外は最高傑作だと自負しています」と語ってくれました。
イングリディさん、またの来日をお待ちしています!
月曜夜8時からは「世界!ニッポン行きたい人応援団」を放送!
▼大工をしていたピーターさんはSNSで見つけた日本の漆器に魅了され、以来独学で漆器を作り続けていた。漆塗り職人のもとで本格的に技術を学ぶのが夢だという。
▼2023年6月、漆のすべてを学ぶために日本を代表する漆器の産地、石川県輪島市へ!
江戸末期に創業した「大﨑漆器店」には1000点もの輪島塗の漆器が展示されているギャラリーがあり、人間国宝の作品などに触れて大感動する。
▼お椀の木地作り、漆の採取、漆塗り、磨きなど、各工程は分業制になっている。それぞれの専門の職人から美しく繊細な技を教えてもらい、本物の漆器作りに初挑戦する。
▼帰国後、教えてもらった技術を駆使してオリジナルの漆器作りに励むピーターさんに、能登半島地震の悲報が舞い込む。お世話になった方々にもう一度会いたいと、震災から2年の時を経て、再来日を果たす。しかし、目の当たりにした光景は想定外のものだった…。
記事提供元:テレ東プラス
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
