ひろゆき×進化生態学者・鈴木紀之のシン・進化論⑬「一般教養は落第ギリギリでも、専門分野の成績だけ異常に高い学生のほうが本当は優秀なんじゃないですか?」【この件について】
 イチオシスト
イチオシスト
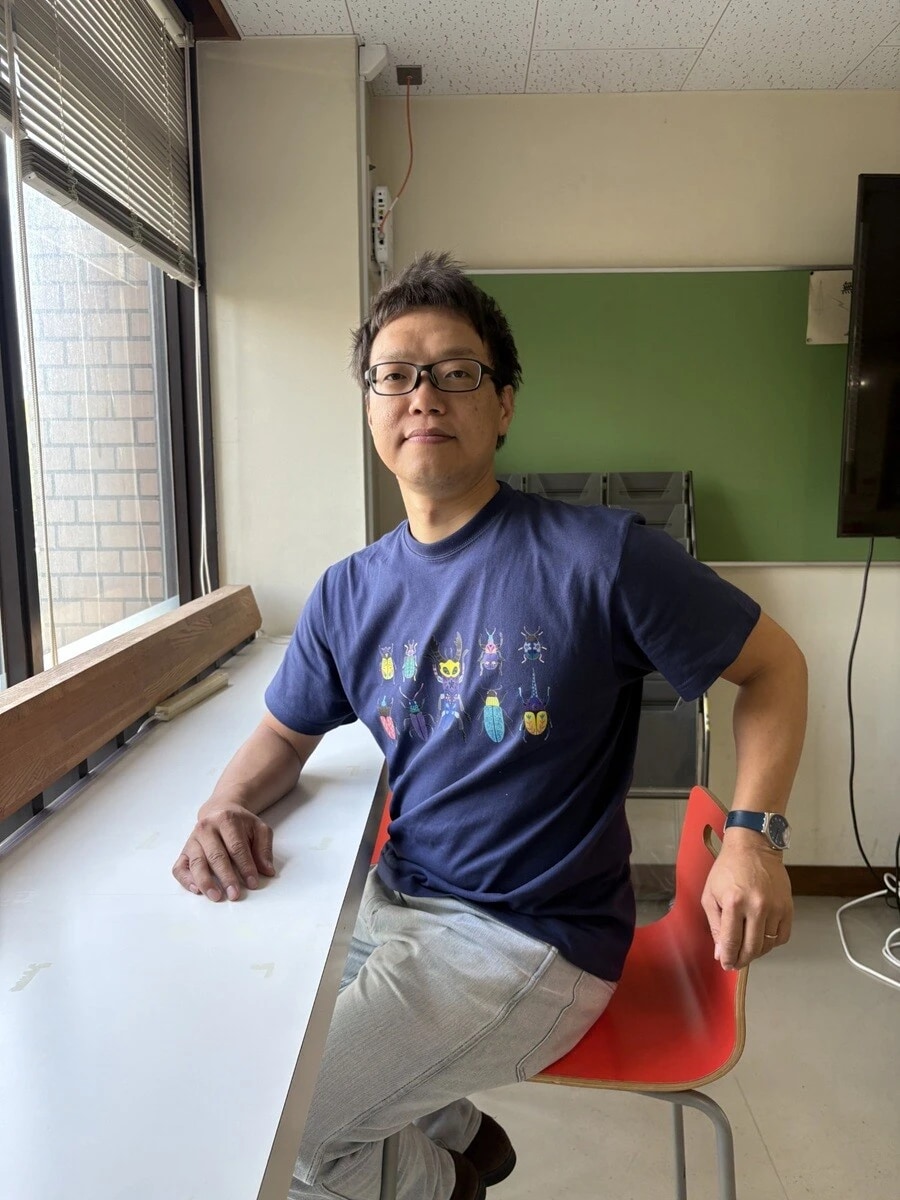
「ダーウィンにとって大きかったのはやはり、若き日のビーグル号での世界一周航海だと思います」と語る鈴木紀之氏
ひろゆきがゲストとディープ討論する『週刊プレイボーイ』の連載「この件について」。進化生態学者の鈴木紀之先生をゲストに迎えた13回目です。
進化論の父、チャールズ・ダーウィンはさまざまな分野で、多くの成果を出してきました。なぜそれができたのか? どんな技術を使ったのか? ダーウィンに詳しい鈴木先生に聞いてみました。
***
ひろゆき(以下、ひろ) ダーウィンみたいな優秀な科学者になる人の条件ってなんだと思います? 実家が裕福だったというのは、すでにお話ししてもらいましたけど。
鈴木紀之(以下、鈴木) 経済的な余裕があると「考える時間」と「試すための時間」を確保しやすいですからね。
ひろ 生物系の研究って、ある程度の実験結果が出た段階で「うん、この仮説は正しそうだ」って、自分の中で満足できちゃうじゃないですか。でも他者を納得させるためには、考えうるすべての反論を潰すようなさらに膨大な実験で理論の穴を埋めなければいけないですよね。
鈴木 そうですね。
ひろ 特に生物学は不確定要素が多すぎて完全に穴を埋めることなんて不可能なのに、自分の中ではもう必要ないと思える作業を延々と続けないと世間は認めてくれない。そのモチベーションってなんだろうと思うんです。
鈴木 実はダーウィンは『種の起源』で、ひと通り自分の理論を説明した後に「本書に対して想定される批判」という章を設けて、あらゆる反論を先回りして書いているんです。
ひろ え、そうなんですか?
鈴木 『種の起源』が出版された後、世界中からさまざまな批判が寄せられました。しかし、その批判のほとんどはダーウィン自身がすでに本の中で想定し、それに対する再反論まで用意していたんです。
ひろ ちなみに将棋の棋士の羽生善治さんは、チェスでも国内トッププレイヤーだったりするじゃないですか。ダーウィンも方法論の横展開というか「こういう素材を集めてこう比較すれば、こういう論理が立つ」みたいな研究方法を確立していたから、さまざまな分野で次々と成果が出せたんじゃないんですかね。
鈴木 その見立ては近いと思います。私が高校生の頃、生物の教科書にダーウィンは2回登場しました。ひとつはもちろん「進化論」。そして、もうひとつが「植物の屈光性」(茎などは光の差す方向に、根は光と逆の方向に向かって成長する)の研究者として登場します。植物の屈光性は、のちに植物ホルモンが発見される下地になったと評価される研究です。
ひろ ダーウィンはよくそこまで実験や研究ができましたよね。
鈴木 当時は統計学が確立される途上にありました。そんな時代に限られた道具と知識で反証されにくい実験を積み重ねた。その執念はすごいと思います。
もちろん、現代的な統計学の視点で見れば不十分な点もあったかもしれませんが、そうした手法が確立される前にあれだけ緻密で膨大な実験を独力で遂行していたというのは驚異的としか言いようがありません。
ひろ その力の源はなんですか?
鈴木 能力の源泉はわかりませんが、私からすると一種の執念のようなものに感じられます。完璧な実験というものは存在しませんが、それに限りなく近づけるための手間と時間を彼は一切惜しまなかった。それくらい徹底していたという印象を受けます。
ひろ そういえば、鈴木先生によるとダーウィンは家に引きこもってたという話でしたよね。普通、自分の理論の穴を見つけるには、友人や専門家など、いろいろな人に読んでもらって意見を聞くじゃないですか。ダーウィンは謎の客観性の持ち主でもあったんですか。
鈴木 そうですね。彼は人類の歴史上でも、最も論理的思考力に優れた人物のひとりだったと言っても過言ではないと思います。
ひろ ダーウィンには卓越した論理的思考力と、常人離れした執念、そしてそれを支える潤沢な資金があったと。
鈴木 そして、やはり大きかったのは、若き日のビーグル号での世界一周航海だと思います。
ひろ そう考えると明確な目的もなく、若いうちに世界中のいろいろなものを見ておく経験って、今の時代でも重要ですよね。んで、あまりに優秀すぎる学生だと、大学卒業後にすぐに大企業に就職したりするじゃないですか。すると、そういう寄り道をする時間がなくなってしまう。
アインシュタインも大学の成績がそこまで良くなかったために大学に残れず、特許庁の審議官になったといわれていますよね。でも、その時間があったからこそ相対性理論の着想を得たなんて話もあります。なんか「大学で優秀すぎないほうが、かえって成功しやすい」みたいな説ってありません?(笑)
鈴木 大学で教えている立場としては非常にコメントしづらいです(笑)。ただ、今の大学生はGPA(グレード・ポイント・アベレージ)、つまり成績の平均点で評価されがちですよね。
ひろ GPAの一般教養の点数が高い学生は、研究者としての才能がないんじゃないかと思いますけどね。専門分野の成績だけが異常に高くて、一般教養は落第ギリギリみたいなとがった学生のほうが、本当は優秀なんじゃないかって。
鈴木 ノーコメントでお願いします(笑)。ただ、一般的に、企業が求める事務処理能力のようなものと、ひとつの分野を深く突き詰める研究者の能力とでは、評価の尺度が違うのは事実です。
ひろ そういう意味では、これは僕の勝手なイメージかもしれないんですが、昆虫研究って世間でいう「ちょっと変わった人」が多い印象があって、社会的な名声や高い評価を得たいと考えるようなタイプの人は、最初から昆虫研究という分野を選ばないんじゃないかと思うんですよ。
鈴木 昆虫の研究者に変な人が多いとは一概に言いませんが、やはりひとつのことに熱中するというのは周囲を気にしていてはできないことだと思います。私自身もそうですが、子供の頃に無邪気にチョウチョウを追いかけていた純粋な感覚が「もう社会人だし」といった意識でだんだん消えてしまう。それこそダーウィンや牧野富太郎といった人物は、尋常ではないレベルで研究に没頭していましたから。
ひろ 牧野富太郎?
鈴木 2023年のNHKの朝ドラ『らんまん』のモデルになった〝日本の植物学の父〟と呼ばれる学者です。ダーウィンも牧野富太郎も周りがどう思うかなど一切気にせず、ただひたすら自分の探究心だけに突き動かされていた。私も含め普通の人間は、社会生活を送る中でどうしても周りの目や常識を気にして無意識に自分にストッパーをかけてしまう。そのストッパーをどうすれば外すことができるのかと考えることはあります。
ひろ でも、そのストッパーって意識的に外せるものなんですか? 外すというより、最初からストッパーがついていなかった人が、その純粋さを保ったまま大人になっただけのような気がするんですよね。
学校の先生に「さあ、皆さん好きなことを見つけましょう」と言われて、「はい。先生、見つけました!」と素直に言うような優等生タイプは、常識を打ち破るような偉大な研究者にはなれないという皮肉な構造がある気がします。
鈴木 私のように「ストッパーをどうやって外そう」と考えている時点で、もう牧野富太郎のようにはなれないのでしょうね(笑)。でも、ダーウィンは本当にそういうタイプだったと思います。
***
■西村博之(Hiroyuki NISHIMURA)
元『2ちゃんねる』管理人。近著に『生か、死か、お金か』(共著、集英社インターナショナル)など
■鈴木紀之(Noriyuki SUZUKI)
1984年生まれ。進化生態学者。三重大学准教授。主な著書に「すごい進化『一見すると不合理』の謎を解く」「ダーウィン『進化論の父』の大いなる遺産」(共に中公新書)などがある。公式Xは「@fvgnoriyuki」
構成/加藤純平(ミドルマン) 撮影/村上隆保
記事提供元:週プレNEWS
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
