ひろゆき×進化生態学者・鈴木紀之のシン・進化論⑧「昆虫の特徴や能力を人間の役に立たせる研究ってどこまで進んでるの?」【この件について】
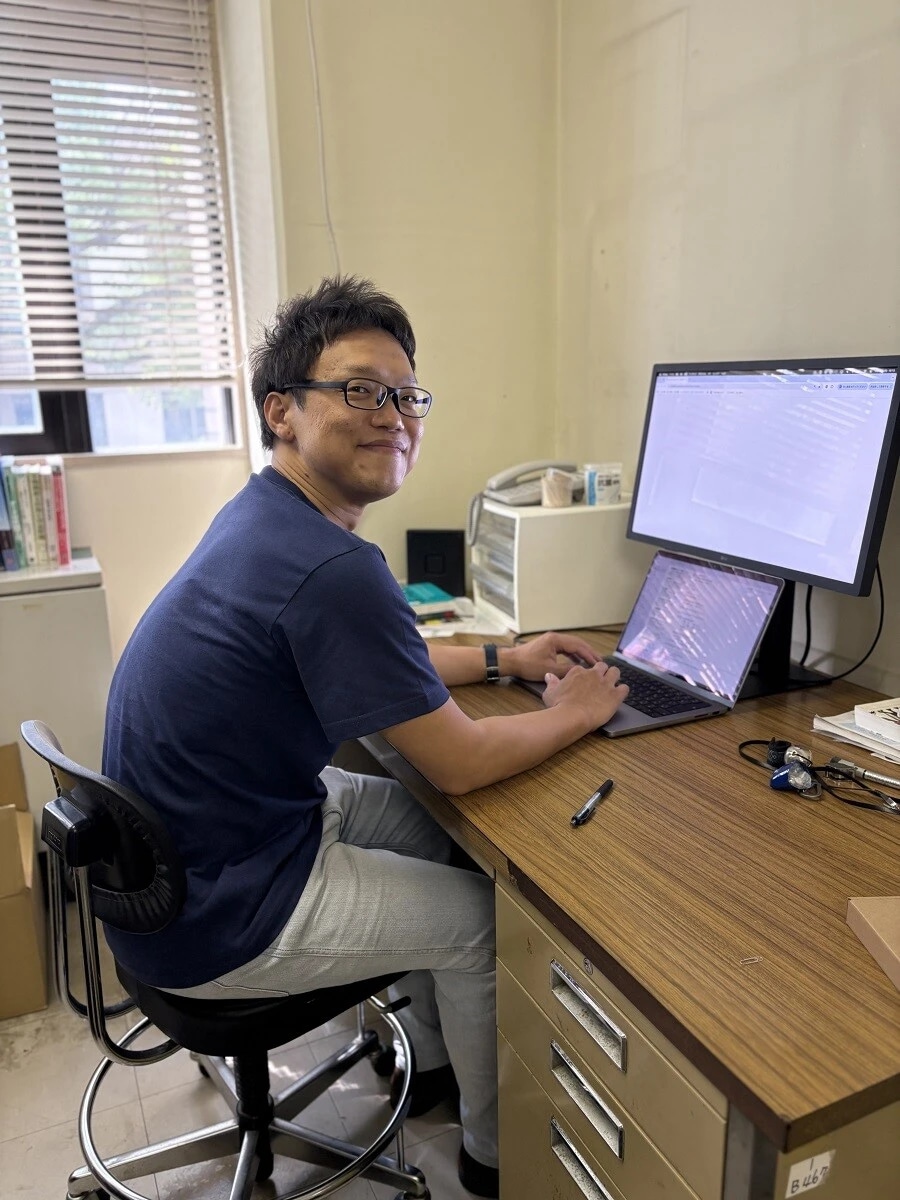
鈴木紀之先生いわく「遺伝子操作した生物を野外に放つという方向の研究は、実際に進んでいます!」とのこと
ひろゆきがゲストとディープ討論する『週刊プレイボーイ』の連載「この件について」。進化生態学者の鈴木紀之先生をゲストに迎えた8回目です。
昆虫はさまざまな特徴や能力を持っていますが、それを人間の役に立たせることができると、人間はもっと楽な生活ができるかもしれません。そんな研究はどこまで進んでいるのでしょうか?
***
ひろゆき(以下、ひろ) 少し前にゴキブリの背中にコンピューターや小型カメラを取りつけて、遠隔操作できるようにするという研究が話題になりました。災害現場や原子力発電所の内部など、人間が立ち入れない危険な場所の調査に役立たせようという試みです。こうした「昆虫を人類の役に立たせる」みたいな研究って、ほかにもあるんですか?
鈴木紀之(以下、鈴木) 昆虫の能力を人間のために利用しようという試みは、大きくふたつの方向に分けることができます。ひとつは、人間にとっての害虫を無害な存在に変えていくアプローチ。遺伝子を操作した生物を野外に放つことについては、生態系への影響や倫理面などハードルが非常に高いのが現状ですが、実際にそういう方向の研究は進んでいます。
ひろ ビル・ゲイツ財団が巨額の資金を投じてやっていますよね。マラリアなどを媒介する蚊のオスが子孫を残せないように遺伝子操作して、個体数を激減させるというプロジェクト。
鈴木 はい。そしてもうひとつが、人間に利益をもたらしてくれる益虫の能力を、さらに伸ばしていこうというアプローチです。例えば、農作物の害虫を食べてくれるテントウムシやミツバチなどがそれに当たります。ミツバチはより多くのミツを集める系統が選ばれてきました。あとはカイコです。カイコはより上質な絹糸を効率良く生産するために家畜化され、品種改良が重ねられてきた歴史があります。
ひろ 古くから人類は、経験則に基づいて地道な改良を繰り返してきたんですね。ただ、現代のゲノム編集(特定の遺伝情報を文章を編集するように書き換える技術)のような技術を使えば、もっと劇的に役立つ昆虫を生み出せそうな気がするんですよ。例えば、鉄よりも強靱な糸を大量に生産できるクモを開発して夢の新素材を作るとか。
でも、植物の品種改良に比べて、昆虫の遺伝子操作が実用化されたという話はあまり聞かない気がします。
鈴木 そのご指摘はもっともです。ただ、そうした研究は今後増えていくと確信しています。技術的な障壁はもうほとんど存在しないといっていいでしょう。近年の遺伝子解析技術の進歩はすさまじく、体の形や色、行動などがどの遺伝子によってコントロールされているのかを特定するのは以前とは比べものにならないほど簡単になりました。さらにゲノム編集の技術を使えば狙ったとおりに生物の性質を改良することも可能です。
ひろ 技術的な問題がないのだとすれば、何が障壁になっているんですか?
鈴木 問題は国民の感情でしょうか。例えば、遺伝子組み換え食品を思い出してみてください。科学的に安全性が証明されていても「なんとなく不安だ」「不自然で気持ち悪い」といった声が根強く、〝消費者の安心〟を得られなければ、広く受け入れられません。
ひろ とはいえ、農作物だとコメやイチゴ、ナシなどは遺伝子組み換えまでいかなくても、品種改良されまくっているじゃないですか。
鈴木 そうですね。もしかしたら、国民の感情というよりも、研究者が世間を気にしすぎているという側面のほうが強いのかもしれません。少し前にコオロギ食を推進していたベンチャー企業が、ネットで批判されましたよね。
ひろ ありましたね。結局、倒産しちゃったんですよね。
鈴木 昆虫食に抵抗がない人々からすればなんの問題もない話なのですが、生理的な嫌悪感を抱く人々が一定数存在し、その声が大きく取り上げられるとビジネスとしては立ち行かなくなってしまう。昆虫に関する科学的な知見は日々深まっていますが、それを社会に受け入れてもらえるかどうかが大きなネックになっていると感じます。
ひろ これは完全に僕の個人的な主観ですが、解剖学者の養老孟司さんや、亡くなられましたけど元国会議員の鳩山邦夫さんのように、昆虫好きとして知られる方って、金儲けに執着がない人が多いような印象があるんですよ(笑)。
鈴木 わかります。
ひろ そこに相関関係ってあるんですか?
鈴木 一概には言えませんが、昆虫が好きな人というのはやはり幼少期からの純粋な好奇心で昆虫を採集したり、標本を作ったりすることに喜びを見いだすタイプが多いと思います。私が言うのも変ですが、少し変わった人が多いかもしれません。
何かに深くのめり込む探求心や集中力を持った人たちですから、そのエネルギーがビジネスに向けばとてつもない力を発揮すると思います。でも、私自身はやはり、生物の素朴な進化の謎を解き明かす研究にやりがいを感じてしまうんです。
ひろ 昆虫が好きな人は、そもそもお金に対する欲望が薄いから昆虫を好きでい続けるのか、それとも昆虫を好きでいるうちにそうした欲望が薄れていってしまうのか......(笑)。鈴木先生の周りにお金儲けが大好きで、同時に昆虫も心から愛しているという人はいるんですか?
鈴木 昆虫好きのコミュニティでは、社会的地位や資産で競い合うというよりも、「どれだけ珍しい昆虫を、どれだけ困難な状況で採集したか」がステータスになったりするんですよ(笑)。
ひろ なるほど。「何日も山奥に分け入って、こんなに珍しい昆虫を発見したんだ!」という武勇伝が、昆虫界では最高の評価を受けるみたいな感じなんですね(笑)。
鈴木 ええ、まさにそうです。
ひろ だとしたら、例えばものすごいお金持ちの昆虫好きが、100人くらい人を雇って「この山の虫を片っ端から捕まえてこい!」と発掘調査的なことをやれば、貴重なコレクションが効率よく集まりそうですけど?
鈴木 実は、それに近い形で採集をしている人は存在します。東南アジアなどでは、現地の人を雇ってとにかく虫を捕りまくる「標本商」がいるんです。そして、そうやって集めた標本を日本のコレクターに販売しているケースがあります。ただ、これはビジネスとしてやっていると言えます。
ひろ そうか。そういう人たちは、昆虫が好きだから採集しているというよりも、儲かる商材として昆虫を扱っているということになりますよね。昆虫好きというわけではない。
鈴木 そうかもしれませんね。
ひろ 多くの子供たちって、昆虫が好きですよね。でも、成長するにつれて昆虫が苦手になっていく。それって「気持ち悪い」「怖い」というイメージを刷り込まれるからだと思うんです。一方で、大人になっても昆虫が好きな人というのは、そうした社会の風潮に流されずに、自分の好きを貫き通せる、ある意味でいちずなタイプの人なんですかね。
鈴木 よく言われるのは、中学・高校での部活動や、恋愛、結婚、就職といったさまざまなライフイベントをきっかけに、多くの人が昆虫趣味から脱落していきます。だから、今、情熱を持って虫を追いかけている大人たちは、それらの〝関門〟をすべて乗り越えてきている相当な〝筋金入りの昆虫好き〟だということです。
***
■西村博之(Hiroyuki NISHIMURA)
元『2ちゃんねる』管理人。近著に『生か、死か、お金か』(共著、集英社インターナショナル)など
■鈴木紀之(Noriyuki SUZUKI)
1984年生まれ。進化生態学者。三重大学准教授。主な著書に「すごい進化『一見すると不合理』の謎を解く」「ダーウィン『進化論の父』の大いなる遺産」(共に中公新書)などがある。公式Xは「@fvgnoriyuki」
構成/加藤純平(ミドルマン) 撮影/村上隆保
記事提供元:週プレNEWS
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
