話題の金髪記者・石田健はなぜいま「儲からない」メディア事業をやっているのか?

「カウンターエリートの主張には賛同できないけど、手を動かしているのはシンプルにすごいと思う」と語る石田健氏
1月のフジテレビの会見で女性への二次加害をたしなめ、〝金髪記者〟として話題になった石田健氏。
大学在学中に起業した会社を上場企業に売却するという輝かしい経歴を持つ彼が今注力するのが、ニュース解説メディア『The HEADLINE』の運営。なぜ彼は、多くのプレイヤーが収益化に苦戦するメディア事業に心血を注いでいるのか!?
■いつかは博士号を取りたい――学生時代に起業されたのはどうして?
石田 初めて会社をつくったのは学部生時代だったんですが、当時はフェイスブック(現メタ)をつくったマーク・ザッカーバーグなどが注目されていて「デキるヤツは起業する」みたいな雰囲気があったから、僕も勘違いしてやってみただけです(笑)。
最初につくったのはアート関連の会社だったんですが、全然儲からなくて。その後はもう少し収益性が高いコンテンツマーケティングの分野に移り、その会社は東証プライム上場企業に売却しました。その後、今の会社を始めたという感じです。
――政治哲学を学びに修士課程に入ったんですよね。それはなぜ?
石田 もともと歴史学に興味があったのですが、今の歴史学は文献を読み込むだけではなく、統計やゲーム理論を応用したり、新しい方法を取り込んだりしています。
そのうち、僕の関心が歴史からそういった手法に移り、結果的に政治哲学を勉強していました。今もアカデミックなことは好きですし、いずれ博士号を取りたい気持ちもあります。
――学問を志向する人とビジネスの世界に行く人とでは、かなり距離があるように思うのですが、石田さんの立ち位置は独特ですね。
石田 うーん、僕はそうは思わないんです。確かに人文・社会科学といった学問とビジネスとの間には距離がある。
ビジネス側は「学者は資本主義のことを理解していないから......」となっていて、一方のアカデミズムの側も、なんとなく「新自由主義はけしからん!」などと、金儲けやビジネスに忌避感を持っていたりしますよね。
でも、それは何か違うなあと思うんです。両者を架橋することはできるはずで、そこにはずっとこだわってきました。
■カウンターエリートとは何か?――2020年にニュース解説メディア『The HEADLINE』を創業されました。一般的にニュースメディアは儲からない事業のイメージがありますが、それでも起業したのはそういう問題意識からですか?
石田 それはまた別ですが、近いものはありますね。社会にとって重要な存在であるメディアが稼げていないという問題がずっと前からあり、実際、マスコミ関係者はずっと「メディアが稼げないのはおかしい。なんとかしないと」と言ってきましたよね。
僕も同意です。特に『ザ・ハフィントン・ポスト』(現ハフホスト)や『バズフィード』といった新興の外資系メディアが日本に入ってきた2010年代には、そういう言説がよく聞かれました。
でも、彼らは10年たっても同じように「なんとかしないと......」と言い続けている。実際に腰を上げて行動に移す人も少しだけいますが、ほとんどの人はトライしないですよね。
「ジャーナリズムとは」とか「メディアのあるべき姿は」みたいな議論をするのは好きなのに、実際に動く人が少なすぎると思うんですよ。まあ、そういう議論も大事なので楽しくやればいいんですが、それとは別に、手を動かす必要がある気がしますね。
――『The HEADLINE』は稼げているんですか?
石田 それほど儲かってはいませんが(笑)、社員にちゃんと給料は出せているし、彼らは良いキャリアを積めていると思います。日本でジャーナリストや記者を志望するというと、お金のことは度外視しないといけないような雰囲気がありますが、それは良くないと思いますね。

石田氏が編集長を務めるニュース解説メディア『The HEADLINE』。月額980円のメンバーシップ制を取っている
――石田さんの考えでは、オールドメディアはどこに活路を見いだすべきなんでしょうか?
石田 うーん、別にわかりやすい正解があるわけじゃないと思うんです。ウチの場合は企業向けに情報をまとめるBtoBの事業に手応えを感じていますが、仮にウチにとっての正解がそれでも、ほかの組織にも当てはまるわけじゃないですよね。
そもそも、「オールドメディアvsソーシャルメディア」という対立軸も、外部が勝手に設定しているだけです。全国に記者を派遣して情報を拾えるのは新聞などのオールドメディアの財務基盤があってこそですから、彼らが残るのは社会にとって重要です。そのためにも稼ぎ方を模索しないといけないよね、というだけです。
――「手を動かすのが大事」というスタンスは、『カウンターエリート』にも反映されていましたね。
石田 そうですね。今、世界中で、マスコミなどの既存エリートを批判する、カウンターエリートたちが注目されています。
トランプ大統領やその周囲にいる起業家や投資家、副大統領のJ・D・バンス氏のような人物です。彼らはしばしばポピュリストであるとか、民主主義の手続きを軽視しているとして既存エリートに批判されていますが、その影響力を無視することはできません。
念のため言いますが、僕は彼らの主張にすべて賛同しているわけではありません。ただ、彼らは「何かがおかしい」という不満をただ抱え込むだけじゃなくて、実際に行動に移していますよね。それはシンプルにすごいと思う。
行動するのって面倒じゃないですか。リスクもあるし、変なところから石を投げられるし。だからみんな口先だけで終わっちゃうと思うんですが、カウンターエリートは、少なくとも実行はしている。
■カウンターエリートは世界を良くするか――本書では、トランプらカウンターエリートの思想を批判的に検証・解説しています。
石田 カウンターエリートは最近になっていきなり出てきたのではなく、その背景にはピーター・ティールやニック・ランドといった思想家たちがいます。
さらに深掘りすると、根底には「努力すれば報われるし、将来の生活は良くなっていくはず」という、戦後世界を支配していたリベラルな価値観が先進国の中間層を中心に崩れつつあることがあるでしょう。
その結果出てきた「何かおかしい」という不満が中間層を新たなナラティブに向かわせて、SNSや動画で直接大衆に語りかけるカウンターエリートたちを登場させた、と言えそうです。
僕が本に書いたそういった背景は、意外と知られていないですよね。
――石田さんは、行動力の面だけは、カウンターエリートを評価している?
石田 繰り返しになりますが、彼らがやっていることには賛成できない部分もあります。でも、「実際に手を動かす人」が少なすぎる気はしますね。
アカデミズムにしてもジャーナリズムにしても、「稼げない」という問題があり、それをなんとかしたいので、僕はいろいろトライしています。そして、答えはひとつじゃなくていいと思うんです。いくつもの出口があるはずなんですが、それは、議論してるだけじゃ見えてこないですよね。
この本には、カウンターエリートを批判している既存エリートの側もカウンターエリートのように行動したら面白いのに、という気持ちも込めています。
――トランプらカウンターエリートの存在が、世界にプラスの影響をもたらすことはあるんでしょうか。
石田 戦争や気候危機など、今の世界が置かれている状況はあまり良くないですが、ありえない話ではないと思います。
カウンターエリートの特徴として、イーロン・マスクのようにテクノロジーとの親和性が高いことが挙げられますが、そういった人材が政治的影響力を持つことが、何か良いものを生む可能性はあります。人類の歴史で、テクノロジーが人類を豊かにしてきたことは確かですから。
差別的な言説とか陰謀論といったカウンターエリートのマイナスの面にはあらがいつつ、彼らの言うことに耳を傾けることはできると思います。
――ひょっとして、石田さん本人もアカデミズムとジャーナリズムの既存エリートに対して手を動かし続けるカウンターエリートですか?
石田 そうなんじゃないですかね?(笑)。僕は社会で何が起こっているかについては興味がありますが、自分自身には全然関心がないんです。
今は目立ったほうが良さそうなので髪を明るくしたり番組でコメントしたりしていますけど、そういうキャラを演じてるだけ。僕の興味は、自分の外に向かって手を動かし続けることにありますから。
●石田健(いしだ・けん)
1989年生まれ、東京都出身。早稲田大学大学院政治学研究科修士課程(政治学)修了後、2015年に創業した会社を東証プライム上場企業に売却。現在は政治や経済、テクノロジー、社会問題などのニュースをわかりやすく解説するメディア『The HEADLINE』で編集長を務める。『DayDay.』(日本テレビ系)や『サンデー・ジャポン』(TBS系)、『ビートたけしのTVタックル』(テレビ朝日系)など多数のテレビやラジオ、雑誌などでコメンテーターを務める
■『カウンターエリート』
文春新書 1188円(税込)
カウンターエリートとは、既得権益化したエリートを批判して支持を集める人々のこと。ドナルド・トランプ米大統領を筆頭に、世界中でカウンターエリートが喝采を浴びている。彼らが台頭した背景や、その裏にある思想を徹底解説する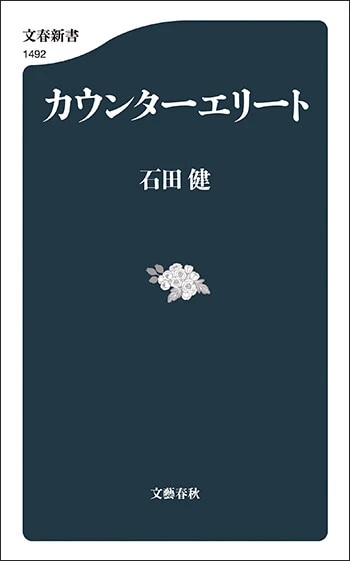
取材・文/佐藤 喬 撮影/文藝春秋写真部(石田健氏)
記事提供元:週プレNEWS
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
