なぜau『LISMO』は『iTunes』になれなかったのか? 着うたが持っていたはずの将来性
auの着うたサービスとして主に名高い『LISMO』を利用していた方は、この記事をお読みの方にも多いのでは?『LISMO』のCMがきっかけとなり00年代に大ヒットを記録した曲も多く、00年代を代表する日本の音楽サービスだと言えるでしょう。
加えて『LISMO』は00年代にすでに、携帯電話とPCを連携させた音楽配信サービスとしても機能しており、携帯電話向け音楽配信とPC連携を実現済み。
同時期に世界的に台頭してきた『iTunes』よりも、携帯電話で音楽を楽しむサービスとしては一歩先へと進んでいた感すらあります。
しかし世界的に定着したのは『iTunes』であり、『LISMO』は最終的に2019年にサービス完全終了に至りました。
なぜ『LISMO』は『iTunes』になれなかったのでしょうか?着うたが持っていたはずの将来性を振り返っていきましょう。
au『LISMO』とは?
au『LISMO』は2006年にKDDIによって開始され、日本国内の携帯電話市場をターゲットにしたサービスでした。LISMOのリスのキャラクターはアイコニックであり、そのデザインを覚えている方は多いでしょう。

00年代の日本ではフィーチャーフォン(ガラケー)が主流であり、携帯電話は単なる通信手段を超えて、音楽やゲームなどのエンターテインメントを楽しむためのデバイスとして進化していました。
そしてガラケー時代を代表する文化は「着うた」「着うたフル」といった短い音楽クリップを着信音として利用するもので、特に若者を中心に大きな人気を博しました。
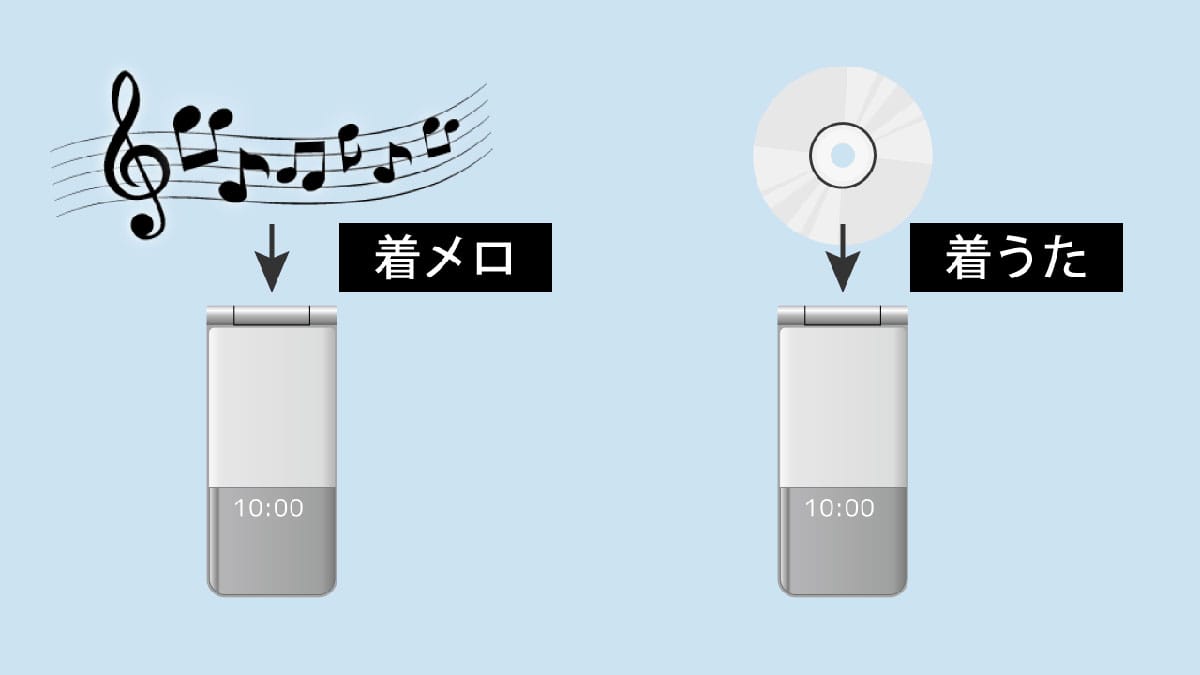
「着うた」「着うたフル」はピーク時(2009年)には、市場規模1,200億円を超えていた一大モバイルコンテンツ。この「着うた」「着うたフル」を代表するサービスこそが『LISMO』であったと言えます。
なお着うたを代表するサービスであったLISMOの影響力は、J-POPそのものにも及んでいました。LISMOのCMといえば、絢香『三日月』やYUI『CHE.R.RY』など。今でもカラオケで歌われる曲も多く、CMソングが国民的名曲として定着する傾向すらありました。
つまり、当時LISMOはそれほどまでに日本の音楽業界に影響力があったと言えます。00年代を代表する音楽サービスが『LISMO』であり、携帯電話で楽しむ音楽として世界的に見ても稀なレベルのリッチさを実現していたと言えるのではないでしょうか。
※「着メロ」は株式会社YOZANの登録商標です。
※「着うた®」、「着うたフル®」、「着うたフルプラス®」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
au『LISMO』と着うたが『iTunes』になれなかった理由
LISMOは着うた文化を象徴するサービスだったと言えますが、着うたは良くも悪くもガラケー時代のサービスに留まったのも事実です。2025年現在における『LISMO』は、今日のiTunesやApple Musicのような存在感があるものとは言えないでしょう。
ではau『LISMO』及び着うた文化が廃れてしまった要因とは、一体なのでしょうか。『LISMO』と着うたが、世界的なサービスへと発展することがなかった理由を見ていきましょう。
【1】キャリア主導のエコシステム
まず『LISMO』に代表される着うたはキャリア主導の閉鎖的なエコシステムに依存しており、他のプラットフォームやデバイスとの互換性が低く、ユーザー体験が制限されました。
LISMOでは、端的に言うと携帯電話と音楽サービスを強く紐づける著作権保護方式を採用していました。その弊害として、同じ番号でかつ同キャリアで機種変更した場合は楽曲の移行は可能でしたが、他キャリアに乗り換えた場合、楽曲の移行はできません。
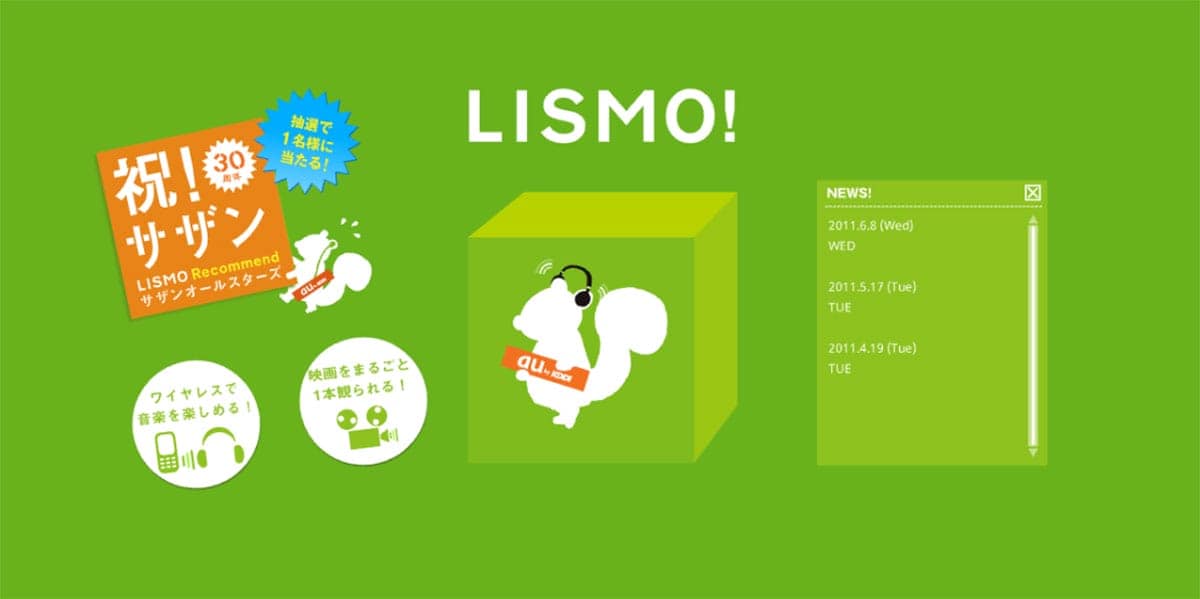
ちなみに、00年代当時はHE-AAC(aacPlus)フォーマットにしか対応していませんでした。
この「ガラパゴス化」した仕様は国内市場には適応したものの、iTunesのように汎用デバイス(iPod)と連携するオープンなエコシステムを構築できませんでした。
なおKDDIは2006年に「au Music Port」という音楽管理システムをリリースしており、着うたフルを扱えたほか、取り込んだCDを携帯電話に転送することができましたが、MP3形式には対応しておらず、一般的な「音楽データ」を扱うことは非常に難しかったと言えるでしょう。
一方でiTunesは、パソコンやiPodといった汎用性の高いデバイスを基盤としており、00年代の時点でユーザーが自由に音楽を管理・再生できる環境を提供していました。
iTunesは、MP3形式やAAC形式の汎用性を活かし、PC・iPod・iPhone間でのシームレスな連携を実現しました。こうしたシームレスさはLISMOが実現できなかったものであり、iTunesが長らく世界的に愛される要因にもなったものでしょう。
『LISMO』のやや閉鎖的なエコシステムが海外で受け入れられるとしたら、そもそもKDDI自体が海外に本格的に進出し、現地のキャリアを買収したうえで『LISMO』を展開するといった工夫が必要だったかもしれません。
【2】「消費」と「保有」の違い
LISMOの収益モデルは、「単曲」単位の課金に偏っていました。着うた(1曲約105円~)や着うたフル(同200円~400円)は、言わばユーザーが「一時的に楽しむ」ためのサービスだったとも言えるでしょう。
15秒~30秒の着信音用クリップが売れる一方で、キャリアを乗り換えた場合に楽曲が引き継げないこともあり、アルバム単位での購入というのは一般的ではありませんでした。
一方、iTunesは1曲150円~250円での販売だけでなくアルバム単位の販売を推進し、ユーザーに「音楽ライブラリの構築」を促しました。こうした「音楽ライブラリの構築」はiTunesの主要な戦略の1つでもあったと考えられ、クリエイターとの直接的な連携も進めていきました。
たとえばiTunesは、レコード会社やアーティストと直接契約を結び、独占配信権ないしは先行配信権や独自の特典を獲得することで差別化を図りました。
2006年にはミュージシャンの氷室京介さんがアルバム『IN THE MOOD』をリリースしましたが、iTunesで予約購入するとライブチケットの先行予約抽選券がプレゼントされるという試みを行っていました。
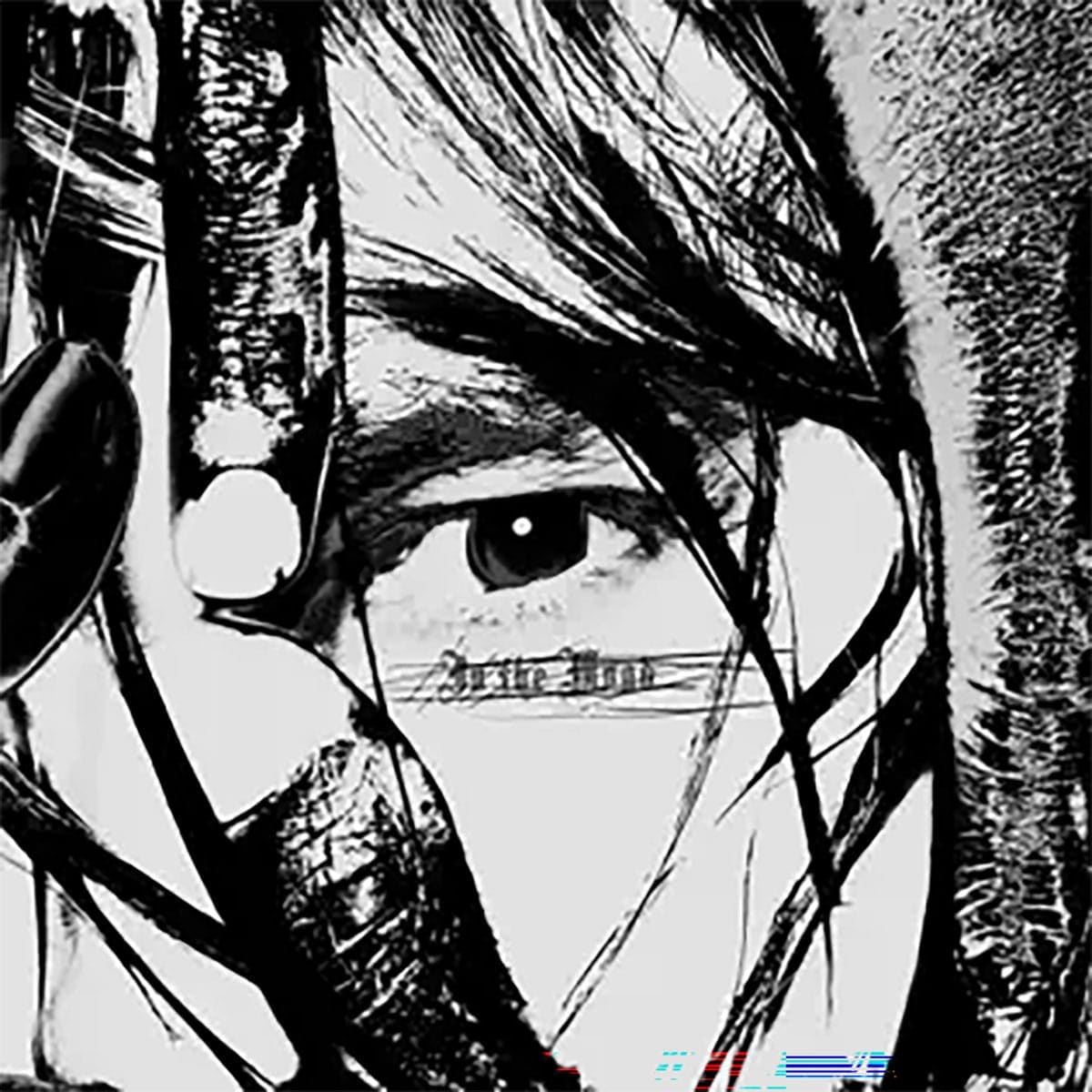
『LISMO』及び着うたは、このようなアルバム単位での購入や長期的な作品の保有をうまく実現しきれなかったサービスと言えるかもしれません。
『LISMO』は日本では音楽サービスというイメージがCMの影響もあり、ある程度一般化しています。とはいえ、それでも世界的に見ると『LISMO』は良くも悪くも着信音の領域に留まったとも言えるでしょう。
【3】ビジネスモデルの違い及びスマートフォン時代の到来
LISMOはau端末でのみ高音質な「着うたフル」が再生可能なDRM(デジタル著作権管理)を採用し、ユーザーを自社プラットフォームに囲い込む戦略を取っていました。つまり、管理が確実になる一方、LISMOは日本市場に特化し、海外展開の計画はほぼなかったと言えます。
また通信料とコンテンツ課金が一体化しており、購入した着うたなどの料金はケータイ料金とあわせて請求されるシステム。プリペイド式のiTunesギフトカードのような柔軟性に欠けた部分もあります。
これに対しiTunesは、「デバイスを超えた音楽ライブラリ」という概念を確立。iPhone登場後は「App Store」との連携でエコシステムを拡張し、2009年にはDRMフリー化を実現。2011年にはiCloudによるマルチデバイス同期を実現した。

Appleは、iTunes Storeを119カ国で展開(2012年時点)、音楽配信だけでなく映画やアプリの販売も統合しました。さらに、2015年にApple Musicをローンチし、サブスクリプションモデルへの移行を主導しました。
フィーチャーフォン時代の技術や端末の仕様、ビジネスモデルに固執した『LISMO』及び着うた文化と、グローバル展開及びスマホの時代へのシフトにスムーズに対応したiTunesの違いはこうしたビジネスモデルの変化や対応方針などに色濃く表れていると言えるでしょう。
『着うた』や『着メロ』が持っていたはずの将来性とは?
00年代当時の日本では、フィーチャーフォン(ガラケー)が全盛期を迎えており、携帯キャリア(au、ドコモ、ソフトバンク)がサービスを主導していました。
その中でも着うたは、携帯電話で音楽を楽しむという新しい文化を創出し、一時は日本の音楽市場を牽引しました。
00年代に周辺機器などを用いることなく、「携帯電話のみ」で音楽配信を実現していた着メロや着うたは世界的に見ても先進的なサービスでした。00年代初頭には、韓国でも類似サービスが登場し、日本の事業者が韓国の事業者向けに着メロの配信サービスを提供する事例も見受けられています。
このように日本の『着うた』『着メロ』は先進的であった反面で、携帯電話向けサービスとして技術的にも権利保護的にもクローズドなものであったことは否めません。クローズドなものとして考えるならば、日本の端末及び通信技術ごとアジア圏のほかの国々に進出することで「アジアならではの巨大な音楽配信サービス」としてより大きな存在感を発揮できるサービスだった可能性があります。
そして『着うた』『着メロ』やその代表的なサービスとしてのLISMOを、よりオープンなものとして捉えるならばスマホへの対応や「DRMフリー」など配信サービスとしての強みを獲得する機会を、自ら逃してしまった感が否めません。
世界的に見ても先進的だったサービスが、スマホ対応が一手遅れたことで大きく後退してしまった、ある意味「悲しい事例」が着うただと言えるかもしれません。
※サムネイル画像は(Image:「au」Facebookより引用)
記事提供元:スマホライフPLUS
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
