「100日ミッション」とエムポックスウイルス(前編)【「新型コロナウイルス学者」の平凡な日常】
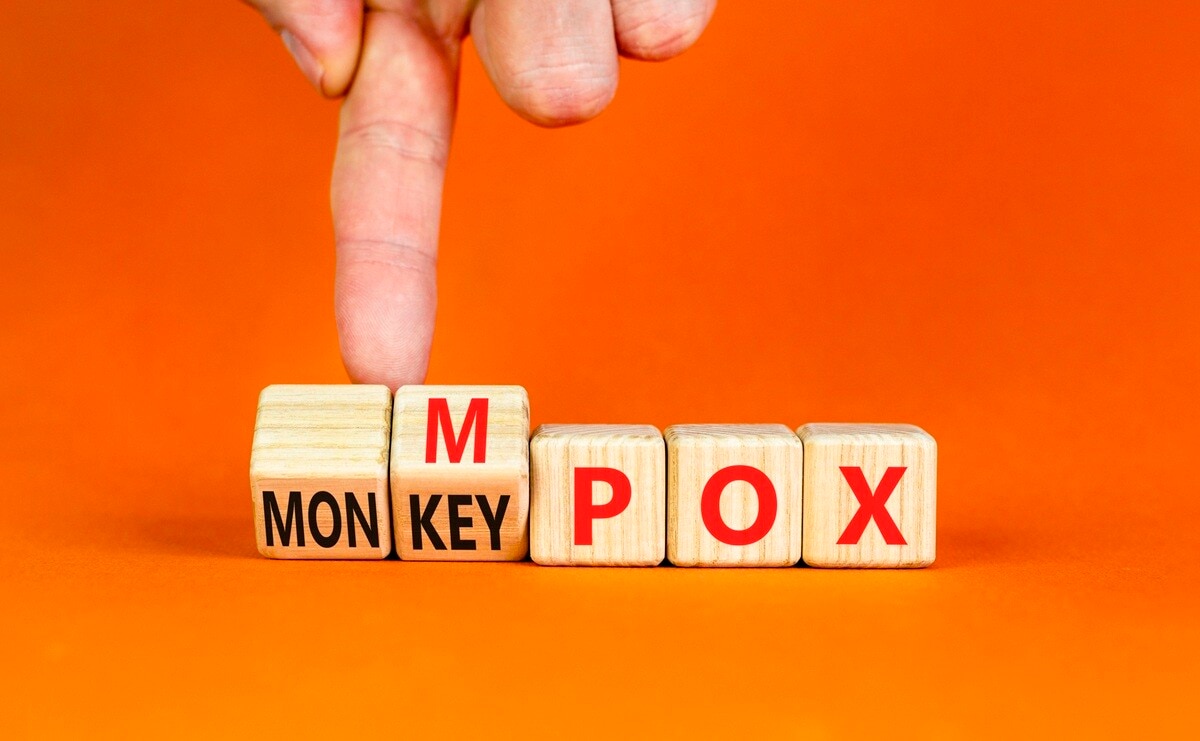
新型コロナパンデミックが収まらない中で出現した「エムポックスウイルス」は、その後、世界各国に広がり、9万人以上の感染者が報告された
mRNAワクチンの技術によって、従来よりもかなり早く承認にこぎつけた新型コロナワクチン。その後のG7サミットでは、ワクチン実用化までをさらに短縮させる「100日ミッション」が掲げられていた。しかし、本当にそれは可能なのか? 2022年に出現して世界各国に広がった「エムポックスウイルス」の研究を例に出して考える。
* * *
■「100日ミッション」とは?2021年6月、イギリス・コーンウォールで開催されたG7サミット(主要国首脳会議)において、「100日ミッション(英語で『100 Days Mission』)」が提唱された。これは、新型コロナパンデミックを受けて、次のパンデミックの際には、世界保健機関(WHO)が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(Public Health Emergency of International Concern、略してPHEIC。日本語では『フェイク』と発音されることが多い)」を発出してから100日以内にワクチンを実用化する! ということを目指した提言である。
これまで、新しいワクチンの承認と実用化には数年から10年以上の時間を要するのが一般的だった。それが、「mRNAワクチン」という画期的な技術の発展によって、COVID-19(新型コロナウイルス感染症)に対するワクチンの使用は、COVID-19に対するPHEICの発出からわずか336日後に承認された。この貢献もあり、mRNAワクチンの実用化につながる技術を開発したふたりの研究者に、2023年のノーベル生理学・医学賞が授与されている(10話)。
この「336日」というのも、過去の例と比較するととんでもない速さだったわけだが、次の感染症有事の際には「100日以内」を目指そう、というわけである。そもそも、そんなことは可能なのか? そして、もしそれにチャレンジするとしたら、どんな課題があるのだろうか?
今回のコラムでは、筆者のとある経験を紹介してみたい。
■「エムポックスウイルス」?新型コロナのPHEICは、2020年3月11日に発出され、2023年5月8日に解除された。
2022年5月6日、つまり、まだ新型コロナのPHEICが継続している中、ある別のウイルスの感染例が報告された。そのウイルスとは当時、「サル痘ウイルス(monkeypox virus)」と呼ばれていたものである。
なおその後、「スティグマ」の観点から、このウイルスの名前は「エムポックスウイルス(mpox virus)」に改められている。ちなみに「スティグマ」とは、「それによっていわれのない差別や偏見につながることを意味する用語」のことであり、最近では、ウイルスの命名の際には特に懸念されているものである(詳しくは9話を参照)。
ちょっとややこしいが、エムポックスウイルスとは、「エムポックス」という感染症の原因ウイルスである。これは、元の表現に戻した方がおそらく理解しやすく、誤解を恐れずあえて旧称で説明すると、「サル痘ウイルスとは、『サル痘(monkeypox)』という感染症の原因ウイルスである」、となる。
それでは、「エムポックス(あるいは『サル痘』)」とはどんな病気かというと、数日発熱した後に、皮膚や粘膜に、特徴的な「膿疱(のうほう)」ができる。いわゆる「膿んだ巨大なブツブツ」である。
エムポックスウイルスは、天然痘ウイルスと同じく、ポックスウイルス科に分類されるウイルスである。ちょっと専門的な情報を付け加えておくと、私が専門にしていたエイズウイルスや、これまで精力的に研究してきた新型コロナウイルスは、「RNA(リボ核酸)」をゲノムにするウイルスであるのに対し、ポックスウイルスは、「DNA(デオキシリボ核酸)」をゲノムにするウイルスである。
さらに、そのゲノムサイズもまさに桁違いである。エイズウイルスのゲノムサイズは約1万塩基、新型コロナウイルスのそれは約3万塩基なのに対し、エムポックスウイルスのゲノムサイズは、なんと約20万塩基である。同じように「ウイルス」とは呼ばれるものの、はっきり言って新型コロナウイルスとはまったくの別モノである。
エムポックスウイルスと天然痘ウイルスは、「膿んだ巨大なブツブツ」という似た病徴を示す。しかし、流行拡大の方法も、その致死率も、天然痘ウイルスとエムポックスウイルスとでは顕著に異なる。
まず、天然痘ウイルスは空気感染することが知られている。そのため、その伝播力はハンパない。それに対し、エムポックスウイルスは、基本的に接触感染で伝播すると考えられている。感染者の「膿んだ巨大なブツブツ」の膿を直接触ったり、感染した人が寝ていたシーツを触ったり(つまり、シーツについていた膿などの体液を触ったり)しないかぎり、感染することはない。
そして、天然痘の致死率は、なんと20~50%と言われている。それに対して、エムポックスウイルスには3種類あると言われていて、致死率はそれぞれ種類によってまちまちである(1~10%と言われているが、これはアフリカでのものなので、先進国ではおそらくもっと低いだろう、とも見積もられている)。ちなみに幸いにして、今回アフリカ以外の国々に広がったのは、致死率が比較的低いタイプのものだった。
■え!! "新型コロナウイルス学者"がエムポックスウイルスを!?エムポックスは、アフリカの風土病のようなものであり、中央アフリカや西アフリカの国々で散発的に報告されていた。つまり、エムポックスウイルスの感染自体には、さほどのニュースバリューはない。
2022年に問題視されたのは、エムポックスウイルスの感染が、イギリス、つまり、アフリカ大陸以外の国から報告されたことにある。これがほかの先進国にも飛び火し、2023年末までに、なんと9万人以上の感染者が、アフリカ以外の国から報告された。
この連載コラムでも何度も紹介しているように、筆者らG2P-Japanはこれまで、新型コロナウイルスの変異株についての研究を精力的に進めていた。その中で、共同研究を進めるにつれて連携が深まり、安定感のある研究基盤が構築できてきているという実感があった。
そんな中、折々に、ある議題について議論する機会が増えた。
私がエイズウイルスの研究から新型コロナ研究に参入したのと同様、他のメンバーも、それぞれが得意とするウイルスを持っていた。
――であれば、これからもわれわれの知恵と技術を結集させれば、どんな新しいウイルスが出現したとしても、それに即時対応できるのではないか? つまり、そんな活動を継続することこそが、「次のパンデミック」に備えるための研究に直結するものなのではないか?
そんな発想を持つようになった矢先に出現したのがこのエムポックスウイルスであり、G2P-Japanの中で、「これにチャレンジしてみよう!」という気概が生まれつつあった。
※2月9日配信の中編に続く
文/佐藤 佳 イラスト/PIXTA
記事提供元:週プレNEWS
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
