難解すぎる「日銀文学」を楽しく読み解くためのヒントとなる一冊を刊行!

「『景気は好調』と『景気はおおむね好調』は同じようでまったく違う。こうした細かいニュアンスは翻訳が本当に大変です」と語る木原麗花氏
数十年ぶりの高インフレや金利上昇という事態を受けて、日本銀行の注目度が上がっている。中でも日銀総裁の発言はメディアをにぎわせるが、関係者の間ではけっこうなクセがあることで知られている。
伝えたいことがあるようで最後はけむに巻いて終わったり、素っ気ない一行が重要な政策転換を意味していたりと、理解にかかるカロリーが妙に高いのだ。
誰が言ったか、この「日銀文学」に長年対峙してきた通信社の記者が、そのワードセンスに着目して特徴を読み解いた新書『日銀総裁のレトリック』が注目を集めている。著者の木原麗花氏を訪ねた。
* * *
――本書を執筆されたきっかけを教えてください。
木原 私は国内のニュースを海外に向けて、英語で発信する記者をしています。基本的には、日銀が出した発表や総裁の発言をそのまま報道します。この仕事を25年やっている中で、総裁によってキャラクターや発信のスタイルがまったく違うな、と感じるようになりました。
特に2013年以降、アベノミクスの推進役となった黒田東彦さんは、異次元金融緩和というパンチの利いた政策を打ち出し、その伝え方もかつてないパワフルなメッセージ性を帯びていました。
それは「黒田バズーカ」といわれたほどで、受け手であるメディアも金融関係者も衝撃を受け、それは間違いなく生活者にも伝わったと思います。
この違いはいったいなんなのだろう?と考えたときに、きっと表現の仕方に根本的な違いがあるのだろうと。
それから大学院に通い、言語学の手法で歴代の日銀総裁が多用した表現、専門用語でいう「レトリック」を分析して、修士論文を仕上げました。これを全面的に、わかりやすく書き直したのが本書になります。
――レトリックの分析というのは、具体的にはどんなことを?
木原 金融政策を決定する会合の後の発表や記者会見の記録が、日銀のホームページに保存されています。作業としては、今から4代前の速水優さんから現職の植田和男さんまでのすべての記録に目を通し、まずは分析のためのルールを作ります。
多用されているワードの分類や、メタファー(たとえ)の種類分けといったことですね。その上で、手作業で該当する表現を拾い上げて記録していきました。
――速水さんから植田さんまでの27年分ですから、とんでもない量じゃないですか?
木原 そうですね。日銀のコミュニケーションで使われた言葉をAIを使ってカウントした研究はありますが、意味内容を押さえたさまざまな表現の収集はおそらく初だと思います。
――そんな手間をかけてまで分析した日銀文学ですが、具体例を教えてください。
木原 「調整」とか「方針」ですかね。誰でもよく使う言葉ではあるんですけど、日銀が使う場合は、具体的に何をしているのか、どんな手段を取るつもりなのか、ということをぼんやりさせておきたいときに使われます。
「モメンタム」「基調」もよく出てきます。モメンタムは物事がある方向に動く力という意味で、基調は物事の流れというくらいの意味ですから、どちらも似た意味の言葉ですね。これは日銀が強気な予測を維持して利上げを正当化したいときに使い勝手のいいワードです。
例えば「物価は基調として上昇しているので利上げする」と言ったとします。そこで目下の経済指標にあまり動きがないように見えても、長いスパンで見て上がっていれば増加基調とはいえますからね。
――あまり自信がない、留保する言葉が多いですね。
木原 そうなんです。あとは「おおむね」とか。基調と似ていますが、「景気の好調はおおむね維持されている」と言うと、所々弱い箇所はあっても、全体としては景気はいいでしょうという感じになります。
海外向けの記事を作っていると、こういう曖昧言葉のニュアンスを伝えるのはけっこう工夫がいるんです。総裁の言葉として曖昧なまま伝えた上で、自分の解釈を補足するようにしています。
――そもそもどうして日銀文学なるものが存在するんでしょうか? スッキリハッキリ伝えたほうが、金融市場にも国民にもメッセージが届きやすいと思うのですが。
木原 日銀にはやはり経済において、巨大な力がありますから。例えば、金融緩和を強化して苦しむ人は少ないと思います。
それが利上げとなると、住宅ローン金利も企業の借り入れコストも上がるわけで、経済に痛みを生じさせます。そうなると、「利上げします!」と勢いよく、強いメッセージを放つわけにはいかないですよね。
――なるほど。日銀のコミュニケーションにはそういう繊細な機微があるんですね。
木原 曖昧にしておく理由はほかにもあります。経済の状況はどんどん変わっていくので、日銀はなるべくいろいろな選択肢を確保したいんですね。取れる手段の幅は広げておきたいし、意表を突いて政策の効き目を大きくするシナリオも保持しておきたい。
言質を取らせないことは、後で文句を言わせない意味でも、政策のインパクトを出す意味でも、とても重要なんです。
――そうなると、木原さんがレトリックについて深掘りするきっかけになった黒田総裁は、やはり異色だったんですね。
木原 おっしゃるとおりで、数値を含めて断言して、政策のインパクトを出すというのは日銀文学史上の発明だと思います。
総裁講演の原稿は「企画局」という部署が作ります。日銀というエリート集団の中でも特に優秀な人材が、イタコのように総裁を憑依させて、総裁のキャラクターと意向に合致した原稿を書き上げます。最後に総裁が手を入れて講演に臨むわけです。
――黒田さんのような発明家のイタコはさぞかし大変だったでしょうね(笑)。最後に、植田現総裁のレトリックの特徴を教えていただけますか?
木原 植田総裁は、経済の動きを「植物の芽」にたとえる表現をよく使います。物価上昇2%達成の「芽」を大事に育てたい、という感じですね。物価上昇の勢いを「力」にたとえる、物理学を連想させる表現も使われます。
このような工夫をしてできるだけわかりやすく伝えたい、でも前任の黒田さんよりは日銀文学らしい曖昧さも駆使するのが、植田総裁のスタイルだといえそうです。
●木原麗花(きはら・れいか)
外資系通信社記者(日銀担当)。1973年生まれ。同志社大学法学部政治学科卒業、早稲田大学大学院政治学研究科修了。時事通信社、米ダウ・ジョーンズ経済通信記者を経て、2006年以降現職。通算20年以上にわたり日本銀行の金融政策の取材に携わり、数々の調査報道に従事。本書が初の著書となる
■『日銀総裁のレトリック』
文春新書 1100円(税込)
日銀の金融政策を解説したり、是非を問う書籍は数あれど、総裁が「何をどう言ったのか」のみに焦点を絞った本はこれが初めてだろう。レトリック分析と呼ばれる手法で、各総裁の比喩やモダリティ(ある事柄に対する話し手の確信度を示す形式。例えば「かもしれない」「必ず」など)に注目し、市場とのコミュニケーションのクセを丸裸に。興味深いデータを眺めているうちに、日銀の次なる一手を読むヒントを得られる、ユニークすぎる一冊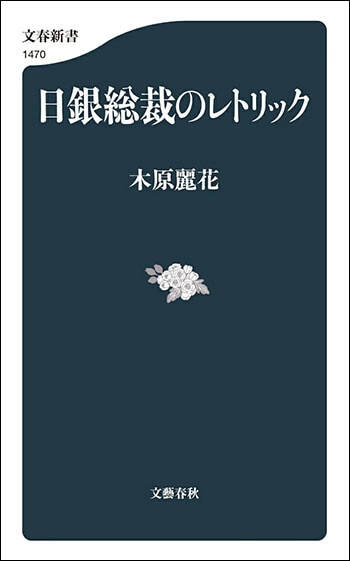
取材・文/日野秀規 撮影/榊 智朗
記事提供元:週プレNEWS
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
