【発火・爆発】「持ち歩く火種」になっていない?モバイルバッテリーの最新リスクと安全対策
今回は、スマホライフPLUS(https://sumaholife-plus.jp/)に掲載された記事を参考に、相次ぐモバイルバッテリーの発火事故と、それに対応する国の規制強化やユーザーの自衛策、最新の安全な製品についてご紹介します。特に、航空機内での取り扱い変更や、リコール情報に気づかない危険性、リン酸鉄・ナトリウムイオン電池のメリットを取り上げます。各項目の詳細はぜひ、スマホライフPLUSでご確認ください。
 イチオシスト
イチオシスト
※記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
発火事故が止まらない!モバイルバッテリーへの対策は?

発火事故が止まらない!モバイルバッテリー
スマホを持ち歩く現代人にとって、モバイルバッテリーは欠かせないアイテム。 ただ、最近は自動車や電車、飛行機などでリチウムイオン電池を使ったモバイルバッテリーの発火事故が報告されており、「大丈夫かな…」と心配になる方も少なくありません。
そこで今回は、スマホライフPLUS(https://sumaholife-plus.jp/)に掲載された記事を参考に、モバイルバッテリーの最新の危険性と対策に関する情報をご紹介。各項目の詳細はぜひスマホライフPLUSでご確認ください。
1:相次ぐ事故で厳格化!航空・鉄道のルール
モバイルバッテリーの発火事故が相次いでいることを受け、公共交通機関での取り扱いルールが強化されています。国土交通省は2025年7月、国内航空会社に対し、モバイルバッテリーの機内持ち込みに関するルールの改定を要請しました。
新しいルールとして、モバイルバッテリーを収納棚に収納せず、乗客が手で持つか、前の座席背面にある収納ネットに入れ、常に状態が確認できる場所で使用することが追加されています。また、鉄道においても、落下や高温になる場所に置かないよう注意喚起が実施されています。
<出典>
「モバイルバッテリー発火」が止まらない! 航空・鉄道・自治体が相次いでルール強化
(スマホライフPLUS)
2:発火の要因となるリコール製品のリスクと自衛策
独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)によると、リコール対象となったモバイルバッテリー製品は直近3年間だけで約59万台となっています。しかし、リコール情報がすべてのユーザーに届かず、経済産業省による資料「リコールの効率向上に向けて」によると、回収率が低い(0〜20%)という現状があります。
自衛策として、まず日本の安全基準に適合した証であるPSEマークの表示を必ず確認すべき。また、充電中や使用中にカイロのように温かくなるレベルを超えて「熱い」と感じる場合や、製品そのものが膨張している場合は、重大な事故に至る前の警告として使用を中止する必要があります。
<出典>
あなたのモバイルバッテリーは安全?発火・リコールが続く理由と安全のためにすべきこと
(スマホライフPLUS)
3:安全性を重視!エレコムの「モバイルバッテリー」

画像引用:スマホライフPLUS(https://sumaholife-plus.jp/devices_gadgets/43375/)
主流のリチウムイオンバッテリーは、製造上の不備や落下、高温などにより発火する危険性があります。こうしたリスクに対し、エレコムからは「ナトリウムイオン」や「リン酸鉄」を採用し、安全性を高めたモバイルバッテリーが発売されています。
リン酸鉄系素材は結晶構造が安定しており、過充電や高温でも構造が壊れにくく酸素を放出しにくいのが特徴です。また、ナトリウムイオンは熱暴走反応が起きにくく、発火しにくい電解液が使われているため、こちらも発火リスクが低いとされています。
<出典>
発火の心配なし!? エレコムの“安全系”モバイルバッテリー2機種を実際に充電テストしてみた
(スマホライフPLUS)
【まとめ】安全なモバイルバッテリー利用のための総括
モバイルバッテリーは便利ですが、発火リスクと無縁ではありません。利用者が安全基準(PSEマーク)の確認や、異常が見られた際の速やかな使用停止を徹底すること、そして国や事業者が定める規制に従った適切な取り扱いを行うことが、安全なスマホライフの鍵となります。
※記事内における情報は原稿執筆時のものです。店舗により取扱いがない場合や、価格変更および販売終了の可能性もございます。あらかじめご了承ください。
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

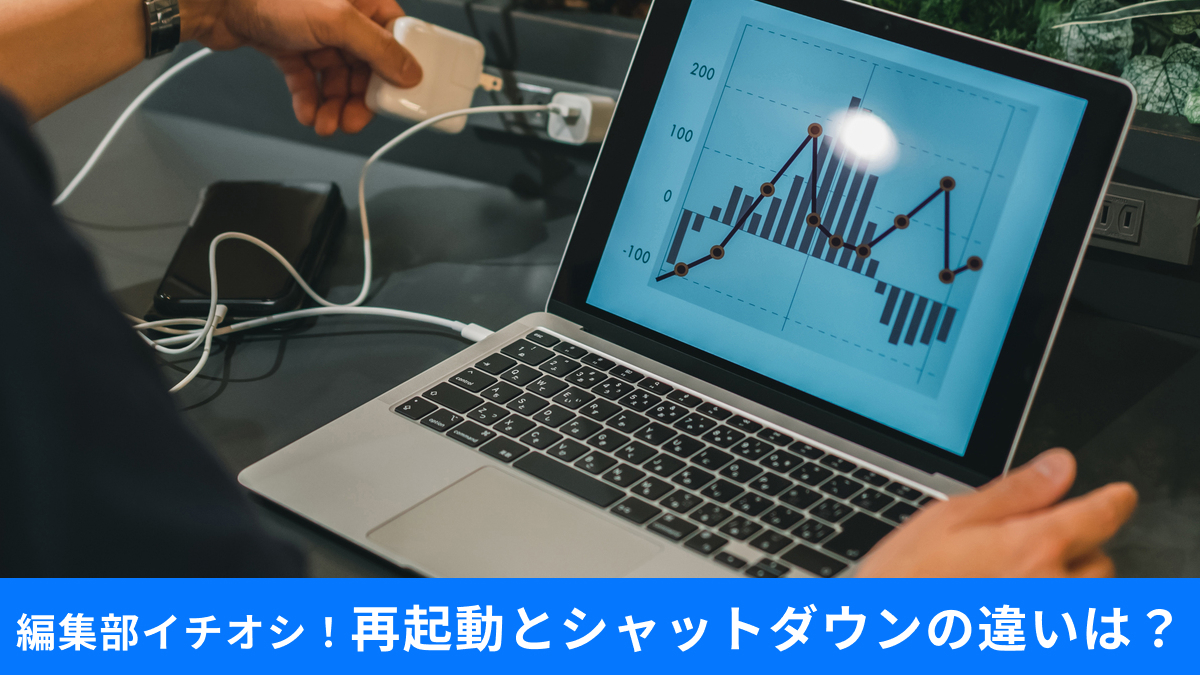)



