注目集めるペロブスカイト太陽電池、新幹線の「防音壁」に取り付けできる? JR東海が実験

2050年カーボンニュートラルの切り札として注目を集める「ペロブスカイト太陽電池」を新幹線の防音壁に取り付けられないか――JR東海がそんなアイデアを検討している。同社は12日、愛知県小牧市の研究施設で次世代太陽電池付き防音壁の試作品を公開した。
ペロブスカイト太陽電池は薄型で軽量、曲げられるほどの柔軟性が特徴。今回の実験で使用されるフィルム型のものは、従来のシリコン系太陽電池パネルと比べると重量およそ1/10、厚さ1/20程度になる。発電効率では従来型にやや劣るものの、低コスト・大量生産に向く。日本が産出量で世界シェアの3割を占めるヨウ素を主な材料としており、特定の国に頼らないサプライチェーンを構築し得る強みがある。政府も「将来性が期待できる技術」としており、早期の社会実装に向けて後押しする。
JR東海とタッグを組むのは積水化学工業だ。同社のフィルム型ペロブスカイト太陽電池は現時点で発電効率15.0%を達成、10年相当の屋外耐久性を備える。発電効率については2030年に18%、将来的には20%以上を目標として開発を進める。幅も現時点ではロール・ツー・ロールで30cmまでだが、2025年度内に1m幅を目指す。ペロブスカイト太陽電池の水に弱いという弱点は、封止技術でカバーする。
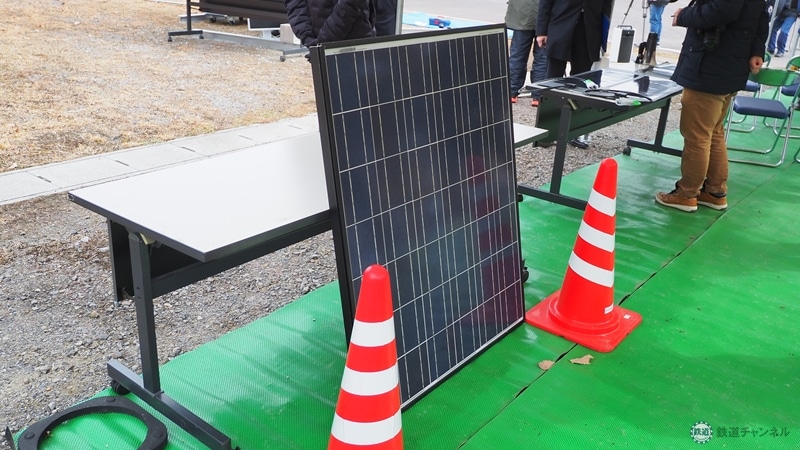
東海道新幹線の営業キロは東京~新大阪間552.6km(実キロは515.4km)、防音壁の延長は約650km。東阪間を東西に走るため、日当たりの良い南側の面積が大きく、太陽光を遮るものも少ない。従来型の太陽光パネルを取り付けるのは難しいが、軽量薄型で曲げられるペロブスカイト太陽電池なら取り付けるハードルは下がり、現実味を帯びる。
実現に向けた課題として、防音壁とペロブスカイト太陽電池の耐用年数の違いを考慮する必要がある。防音壁は30年以上持つが、ペロブスカイト太陽電池の寿命は今のところ10~20年と短い。長期の運用を考えるなら防音壁と一体化させるのではなく、太陽電池だけを取り換えられる構造とした方が良い。そこで、JR東海は脱着可能なガイドレール構造を考案し、太陽電池を下から曲げ入れられるようにした。

試作品の防音壁で太陽電池を取り替える様子も公開された。まずはねじ止めされた支持枠を外し、太陽電池をガイドレールに沿って取り外す。要した時間は2人がかりでおよそ1分半ほどだった。取り付けは逆の手順で行い、2分半ほどで終了した。

JR東海は1月半ばに防音壁の試作品を完成させ、課題の抽出を目的として発電量の計測等の実証実験を開始した。東側・南側以外の条件を揃え、発電量や日射量の測定、耐久性を実時間軸で検証していく。平たく言えば1年間置きっぱなしにして、実際の発電量などを見ていくということだが、紫外線を当てるような試験も別で行う。
新幹線の運行による風圧や振動に耐えられるかどうか、といった課題もある一方で、日照量の少ない曇りの日でも発電できるなど期待を寄せられる結果も出ている。発電した電気は主に新幹線の駅などでの使用を検討しているという。
記事:一橋正浩
記事提供元:鉄道チャンネル
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
